平成28年度 社会科総論
社会科研究主題
社会認識を高める授業の創造
~社会的事象から見いだした「かかわり」を表現する活動を通して~
中田 敦 小林淳真 奥田陽介
1.主題設定の理由
(1)本校生徒の実態から
本校生徒の社会科における学習到達状況は、過去数年のCRTの結果から「社会科的な思考・判断」「資料活用の技能・表現」の数値が、「知識・理解」とくらべて、若干低い傾向にある。ここ数年「思考・判断」「技能・表現」の数値が低かった要因として、ある特定の事象しか説明することが出来ない固定的な知識となっていたためと考えている。
授業において私たち教師は、生徒に単に固定的な知識を詰め込むのではなく、「生きて働く知識」(学習や日常生活で出会う問題に生かすことができ、他の事象や事例に応用・転移できる知識~事象間の関連を自ら見出し、そこから社会を見つめなおすことが可能な知識~)へと高めていくことが大切である。
そこで、前研究においては、『かかわり』を意識させる授業の実践に取り組んできた。その結果、「思考・判断」の力は高まってきたと感じている。しかし生徒は「生きて働く知識」を習得できるようにはなってきたものの、それを他者に表現することを苦手とする生徒がまだまだ多いのが現状である。本研究では、昨年度まで取り組んだ、社会的事象から見いだした『かかわり』を他者に伝える学習活動を授業に積極的に取り入れていきたい。「技能・表現」の力を高めると共に「思考・判断」についても、さらなる向上を図っていくことを目指したいと考える。
(2)本校社会科が考える「社会科の課題」
これまでの本校社会科の研究、また本校生徒の実態から、社会科の教育を改善していくために必要なことは、以下の二つであると考える。
一つは、生徒が地理認識、歴史認識や政治経済認識(以下、社会認識)について、現代社会を理解する上で有意義なものにすることである。言いかえると、生徒自身が既に持っている知識に、新たなものを加えたり、また組み替えたりして、社会認識を育て、高めていくことである。
もう一つは、社会認識を高めるために、生徒が主体的に学習していける方法を工夫することである。つまり、社会的事象の見方・考え方といった「社会を見る眼」を育み、それを将来に渡って高めていけるように、生徒自身が主体的に考え、自分なりに納得できる学習を可能にすることである。
(3)昨年度の成果と課題
昨年度、本校社会科では「社会認識を高める」ことを目標に掲げて、授業実践を中心に取り組んできた。授業ではこれまで研究を重ねてきた「かかわり」を、生徒に意識させたり、見いださせたりする場面を設定してきたことで、社会科における「かかわり」についての理解も徐々にではあるが生徒たちに浸透し、思考力・判断力の向上にもつながってきている。また、本校全体研究で重視している「表現活動」も思考力・判断力をさらに向上させ、社会認識を高めるために学習活動に取り入れてきた。
まず歴史的分野では年表の作成を行った。基本的に単元のまとめとして取り入れ、時代を大観すること、歴史の流れを大きく読み取ることを第一に既習事項を整理しながら作成させた。この学習は歴史の大きな転換点はどこかを考え区分するもので、各自が自分なりの根拠をもって区切り、級友に伝え合うことを行った。これは、前述した「思考力・判断力も高め、社会認識を高める」ことをねらいとしたものである。伝え合う活動によって、より深い思考を促し、理解もより確かなものになったのではないかと考える。
地理的分野では、自宅周辺の略地図を作らせ、地域に見られる事象の分布の様子や地域を象徴する事象を書き込んでまとめることによって、身近な地域の特色を明らかにさせた。また1、2年生それぞれが、各自が選んだ都道府県・国の調べ学習を行い、この学習のまとめとして級友に伝え合う活動を今年度も取り入れた。さらに2年生から1年生へ、学年間を越えた国調べのプレゼンテーションも行った。この学習を通して調査内容に加えて表現する方法についても、1年生は2年生から学んだ。この学習の課題として、社会的事象の視点の関連についての説明が不十分であるなど、生徒によって調査内容に不備も見られたが、少人数で伝え合う基礎は身についてきていることを我々教師は実感することができた。
3年生の公民的分野では財政の諸問題を通して、将来の国家像を描き予算を考えさせる授業に取り組んだ。成果としては、日本の課題を個人で考え、それをワークシートにまとめたものを級友に説明することによって、自らの考えを再度考察し、より深く将来の国家像について考えられるようになったと思う。課題としては、生徒が自らの変容を見取ることができるように、事前・事後調査を行うこと。またいつ、どのように自分自身の考えが変わったのか気付かせること、そして生徒の思考を最大限引き出すための学習意欲を高める工夫の必要性、さらには社会認識を高めるために話し合いを機能させる工夫が必要であることなどが挙げられた。
昨年度は3分野を通して、表現活動を通して社会認識を高めるだけでなく、その達成の「見取り」も研究の対象としきたが、評価方法等をまとめきれなかった。生徒の多用な思考や判断がどう向上してきたのか、生徒自身が認知し、また教師も次の授業に生かすためにも3か年の最終年度である本研究において、評価の方法についてもまとめていきたい。
(4)全体研究とのかかわり
①「かかわり」を見いだす課題・活動の設定について
今年度の本校全体研究でも、これまで8年間研究してきた「かかわり」を生かした授業に取り組んでいきたいと考えている。
『かかわり』とは、「学習内容の関連性」を指している。本校では具体的には次の3つを考えている。
| ①教科の学習内容同士のかかわり ②教材の持つ学問の体系的なかかわり ③教材と日常事象とのかかわり |
中学校社会科では1、2年生で地理・歴史的分野を並行して学習したのちに、3年生で公民的分野を学習す
る。このねらいは、各分野間の学習内容の関連性から課題を見いだし、3年次の公民的分野につなげて、3年間を通して公民的資質を高めていくことにある。π型と呼ばれるこの3年間の学習過程そのものが、「かかわり」を追究する要素を持って構成されている。社会科そのものが「かかわり」の教科であると言っても良い。
また各単元において学習する社会的事象は、その社会的事象だけで成り立っていることなどあり得ない。ある事象には、それが成り立つ原因があり、またそれがもたらす影響や結果がある。他のさまざまな事象がいくつも関連し合って、一つの社会的事象は存在しているのである。したがって学習する上で、一つの事象を理解するためには、必ずいくつかの事象も関連づけて理解していく必要があるし、そうでなければ本当の意味で理解したとは言えないだろう。
本校社会科では、「ある事象と事象の間から見えてくること」を、『関連性』と定義することとした。さらに『関連性』から、現代の社会を読み解き、自分たちの社会を見つめ直す、課題を見いだす、今後を予測するなど、『関連性』から生じた多様な判断について『吟味・検討』することを、本校社会科では『かかわり』と定義した。
本年度本校社会科は、全体研究のテーマ「 知の再構成を目指して ―「かかわり」を生かした学習過程の工夫― 」を基本として、「かかわり」を生かした授業を工夫、実践していくことを目指すこととした。
社会科の学習における「かかわり」については、社会科総論4~5ページの『☆各分野における「学ぶ力」』に(斜線・太字)で示したが、新しい学習指導要領への対応もかねて、「学ぶ力」及び「かかわり」をベースとして社会認識を高める授業の工夫と実践に取り組んでいきたい。
②学んだことを伝える活動について
社会科の授業では、単純な知識等を問う発問に対しての発言は比較的あるものの、自分の考えを問われる発問や討論する場面になると消極的になる傾向にある。この原因として、自己の学習内容の理解に対する自信の無さ、また意見を主張することに対する遠慮が考えられる。これらを克服し、表現する力を身につけていくには、ある程度繰り返して「伝える活動」を授業で取り組んでいく必要がある。
伝える活動を通して生徒は、他者に正確に伝えるためには、伝え方に工夫が必要であることや、より確かな理解を必要とすることも考えるに違いない。また伝えることを通して、相手からの情報を受け取り方、聴き方についても改善の必要性を感じるかもしれない。このことに関して教師自身にも、これらに気づかせる指導や助言がタイミング良く行っていく必要がある。
このように他者に伝える活動に取り組んでいくことを通して、表現する力に加え、同時に思考・判断する力を使う必要にも迫られるし、他者の発言を聴くことは、自己の理解の深まりにもつながるのである。これは(2)に先述した本校社会科が考える本来的課題「社会認識を育て、高める」上で、たいへん有効な活動であると考える。「伝える活動」(表現活動)を積極的に取り入れてた授業の創造を社会科の授業研究においても深めていきたい。
(5)学びを見取る評価について
上記①・②を取り組んでいく上で、生徒の学びの変容を見取ることは大変重要である。生徒が社会的事象の
「かかわり」を見いだすことができたかのか、「かかわり」を表現する活動が学習としてなりたったのかどう
か。それらを教師はしっかりと見取り、授業に生かしていくことが必要であろう。
今年度の研究も、①・②を取り入れた授業の工夫と実践を研究の中心に据えたが、各授業における評価の方法もワークシートや評価表等を工夫していきたいと考える。
(6)「かかわり」を表現する活動について
新しい学習指導要領には、「社会科各分野の共通の目標を目指し、社会的な見方や考え方を養うことをより一層重視する観点に立って、社会的事象の意味、意義を解釈する学習や事象の特色や事象間の関連を説明するなどの、言語活動を一層充実する」(「中学校学習指導要領解説 社会編~文部科学省~」改訂の趣旨p8より)と記されており、言語活動の充実は今回の改訂の主要事項となっている。
本校社会科で取り組む「表現する活動」は、この言語活動に他ならない。社会的事象から見いだした「かかわり」を表現する活動は、新学習指導要領の趣旨を生かすことにつながるものと考える。
さらに「(1)生徒の実態から」で述べたように、本校生徒の「表現することを苦手とする生徒が多い」という課題を考えた上でも、取り組むべき活動であると考えた。
社会科の表現活動として、次のような活動を考えている。
①個人 … 地図、レポート、新聞等の作成
②小グループ… KJ法など取り入れたワークショップやミニ討論
③学級 … パネルディスカッション、ディベートなどの討論
学習の形態によって、このように分けてみたが、単元の特徴や目標また生徒の実態によって、さまざまな表現活動が考えられるし、①~③を組み合わせた学習もあるだろう。今年度は、各分野の各単元で、どのような表現活動が有効であるか、まず授業で実践して検証していきたい。
2.研究目標
⑴ 社会認識を高めていくための「知」を「かかわり」でつなげた授業の実践
⑵ 表現活動を取り入れた授業と見取りの工夫
3.研究内容と計画
⑴ 研究内容
①「学ぶ力」の育成
ア 新学習指導要領に対応した「学ぶ力」の内容の具体化
イ 表現活動を通しての「学ぶ力」の育成
②『かかわり』を意識した授業構成
ア『かかわり』の内容の明確化
イ『かかわり』から見いだした内容を表現する方法の検討
③ 上記内容を踏まえた授業実践とそのフィ-ドバック
ア「学ぶ力」を身につけるための授業の工夫
イ『かかわり』を見いだすための授業の工夫
ウ ア・イをもとにした授業実践(フィ-ドバック)
⑵ 研究計画
◎ 1年次
①「学ぶ力」を身につけ、『かかわり』を表現する授業の工夫と授業実践
② 各分野における「学ぶ力」と『かかわり』の関係構造の明確化
◎ 2年次
①「学ぶ力」を身につけ、『かかわり』を表現する授業の工夫と授業実践
②「学ぶ力」『かかわり』の関係構造をふまえた年間指導計画の検討
③ 表現活動を取り入れた授業における評価規準の検討。
◎ 3年次
① 1、2年次の実践を踏まえた、「学ぶ力」『かかわり』の内容・関係構造の検討
② ①を踏まえた、年間指導計画の作成
③「学ぶ力」を身につけ、『かかわり』を表現する授業の工夫と授業実践
④ 表現活動を評価するための規準の作成。
4.本年次の研究内容
(1) 表現活動を取り入れた授業の工夫と実践
本校社会科では各分野における「学ぶ力」の内容・関係構造について、系統だったものを作成してきた。これまでも【「学ぶ力」の具体化】と【『かかわり』の明確化】を通して、社会科授業のあり方についての検討を重ね、社会的事象から見出した「かかわり」を表現する活動を通して、思考力・判断力をさらに向上させる授業の創造に取り組んできた。
今年度の研究も、昨年度までの研究の継続を基本とし、生徒が社会的事象間から見いだした『かかわり』を他者に伝える活動等を通して、社会認識をより高められる授業を工夫・実践していきたい。さらにそのために有効と思われる「社会科としての表現活動」を、授業に多く取り入れていく中で、その有効性について検証して、表現活動のバリエーションを増やしていこうと思う。
(2) 表現活動を取り入れた授業の年間指導計画と評価規準の検討
新学習指導要領への移行にあたって、各分野ごとに表現活動を盛り込んだ年間指導計画、評価の方法についても取り組んでいきたい。
また、表現活動を取り入れた授業によって、生徒がどう変容し、授業がどう変わったかが明確になるような評価(見とり)を行っていかなければならないと考えている。
☆各分野における「学ぶ力」《※下線部(斜字・太字)は、本校の社会科で目指す『かかわり』の内容。》
〔地理的分野〕
○事象を空間的視点によってとらえるための「学ぶ力」
ア 事象を位置・分布という視点からとらえることができる。
イ 事象を空間的な広がりという視点からとらえることができる。
ウ 一定の事象によって地域を区分することができる。
○さまざまな事象を結びつけて、各地域の社会の営みを読み解くための「学ぶ力」
エ 各地域の自然事象を結びつけることによって、人々の行為の前提となっている条件を見定めるこ
とができる。
オ 各地域の政治・経済・社会事象を結びつけることによって、人々の行為の社会的要因を見定める
ことができる。
カ 地域内や他地域との機能的関係をつかむことによって、人々の行為にとっての空間を見定めることができる。
キ 一定の空間における自然的前提条件や社会的要因のもとで、人々の行為による各地域の社会の構
成を読み解くことができる。
○他地域との対比や関連において、自分たちの社会を見つめなおすための「学ぶ力」
ク さまざまな視点から他地域の社会と自分たちの社会とを対比することができる。
ケ さまざまな視点から他地域の社会と自分たちの社会とを関連づけることができる。
コ 自分たちの社会を空間的関係において見つめなおすことができる。
〔歴史的分野〕
○事象を時間的視点によってとらえるための「学ぶ力」
ア 事象を時期という視点からとらえることができる。
イ 事象を時間的なつながりという視点からとらえることができる。
ウ 一定の事象によって時代を区分することができる。
○さまざまな事象を結びつけて、時々の社会の営みを読み解くための「学ぶ力」
エ 時々の人々の行為の歴史的背景を知ることができる。
オ 時々の政治・経済・社会事象を結びつけて、人々の行為の社会的要因を理解することができる。
カ 時々の社会の動向を、人々の行為と結びつけて把握することができる。
キ 一定の歴史的背景や社会的要因のもとで、人々の行為による時々の社会の構成を読み解くこと
ができる。
○過去との対比や関連において、自分たちの社会を見つめなおすための「学ぶ力」
ク さまざまな視点から、過去の社会と自分たちの社会とを対比することができる。
ケ さまざまな視点から、過去の社会と自分たちの社会とを関連づけることができる。
コ 自分たちの社会を時間的関係において見つめなおすことができる。
〔公民的分野〕
○他地域や過去の社会との関係、および個々人の生活との基本的関係から、現代社会の成り立ちを巨視的にとらえるための「学ぶ力」
ア 現代日本社会を地理的世界のなかに位置づけてとらえることができる。
イ 現代日本社会を歴史的世界のなかに位置づけてとらえることができる。
ウ 人々の生活を社会との相互的な関係のなかに位置づけてとらえることができる。
○さまざまな事象を結びつけて、社会の各領域の営みを読み解くための「学ぶ力」
エ 経済事象を結びつけて現代社会の仕組みを見定めることができる。
オ 政治事象を結びつけて現代社会の仕組みを見定めることができる。
カ さまざまな経済事象や政治事象を結びつけて現代社会や社会生活の構成を読み解くことができる。
○現代社会の課題を見出すとともに、自他の判断を吟味・検討するための「学ぶ力」
キ 現代社会の今後を予測することができる。
ク 現代社会の課題を見出すことができる。
ケ 現代社会の課題をめぐる多様な判断を吟味・検討することができる。
※本校における「学ぶ力」の育成の構造図
|
|
( 公 民 的 分 野 ) |
|
|||||
|
( 地理的分野 )
⌒
地 理 的 分 野
|
現代社会の課題を見出すとともに自他の判断を吟味・検討すること |
( 歴史的分野 )
⌒
歴 史 的 分 野
|
|||||
|
さまざまな事象を結びつけて社会の各領域の営みを読み解くこと |
|||||||
|
他地域との対比や関連において自分たちの社会を見つめなおすこと |
他地域や過去の社会との関係および個々人の生活との基本的関係から,現代社会の成り立ちを巨視的にとらえること |
過去との対比や関連に おいて自分たちの社会を見つめなおすこと |
|||||
|
さまざまな事象を結びつけて各地域の社会 の営みを読み解くこと |
さまざまな事象を結びつけて時々の社会の 営みを読み解くこと |
||||||
|
空間的視点によって事象をとらえること |
時間的視点によって事象をとらえること |
||||||
|
|
|||||||


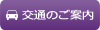



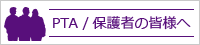

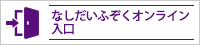

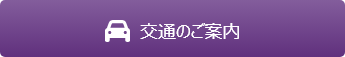
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp