学習過程を意識した「書くこと」の指導 (平成23年 望月)
2011年7月27日
山梨総合教育センター
B 「書くこと」講習会
学習過程を意識した「書くこと」の指導
望月 陵(山梨大学教育人間科学部附属中学校)
キーワード 言語活動例 学習過程
概 要 新学習指導要領の柱となっている言語活動例を軸にしたB領域の実践。
I 新学習指導要領について
【 改訂のポイント 】
- 3領域1事項 伝統的な言語文化と言葉の特質に関する事項
- 学習過程の明確化
- 言語活動
【 今なぜ、言語活動の充実か?】
(第3回ことばと学びをひらく会 2009年10月24日 横浜国立大学 高木まさき氏講演より) 1)新学習指導要領の「言語活動例」は何が違うか。
2) 国語科の言語活動モデル
3) 活動で学びはどう変わるか?
4) 旧来の国語科の学習)(読解中心)
具体的、立体的、プロセス
画像
テキスト(教師) → → 学習者 言語活動(読み取り・解釈・注入)
5) 言語活動で、学びのリソースをリンクさせる。
画像
他者(友だち、教師、家族など)
情報 言語活動 対象
画像
画像
画像
6)他教科との連携の仕方
7)改めて、今なぜ言語活動か?
- 思考力・判断力・表現力等の育成
- 中教審答申(2008年1月17日) 学習活動=言語活動
8)その背景は
- 「知識基盤社会」の時代と「生きる力」
- 教育課程実施状況調査、PISA、TIMSS、全国学力・学習状況調査 9)言語活動で学びを活性化する
- 読解から読書へ、読書から読解へ
- ノートを活用する(ワークシート偏重から)
板書、整理、気づき、疑問、考え、練習、学習の反省、過程重視→ 思考訓練のため 10)言語活動が平板。仲間内の言葉 - 心情を豊かにし、人間関係を創る語彙の不足。
(言語、メディアなど)
(人、社会、文化、自然)
1
2011.7.27
山梨県総合教育センター B「書くこと」研修会
II 指導計画作成の流れ
- 学習目標を明確にする。
- 効果的な言語活動を。
- 学習過程を意識させる。
- 評価。
- 生徒の実態 ・年間指導計画
- 言語活動例を参考に ・他教科との連携。
- 学習の見通しをもたせる ・評価の観点を明確に。
- 言語活動を意識した評価設定。 ・生徒にいかに返すか。 ・年間指導計画の見直し。
画像
画像
III 実践例
| ア | イ ウ | ||||
| 話すこと・聞くこと | 話題設定や取材 | 話すこと(話の準備)(話す) | 聞くこと | 話し合うこと | |
| 課題設定や取材 | 記述 | ||||
| 読むこと | 語句の意味の理解 | 文章の解釈 | 自分の考えの形成(形式について)(内容について) | 読書と情報活用 | |
< 言語活動例との関連 >
(学習過程を設定するメリット)→ 生徒が学習の見通しをもつ 1 児童・生徒の主体的な学習を促す
2 他教科等の学習や生活に役立つ
3 系統的な指導を行いやすくする
2
2011.7.27
山梨県総合教育センター B「書くこと」研修会
【「書くこと」の系統性】
| 第5・6学年 | ||||
| 話題設定や取材 | ア 考えたことなどから書くことを決め、目的や意図に応じて、書く事柄を整理すること。 | ア 日常生活の中から課題を決め、材料を集めながら自分の考えをまとめること。 | ア 社会生活の中から課題を決め、多様な方法で材料を集めながら自分の考えをまとめること。 | ア 社会生活の中から課題を決め、取材を繰り返しながら自分の考えを深めるとともに、文章の形態を選択して適切な構成を工夫すること。 |
| 構成 | イ 自分の考えを明確に表現するため、文章全体の構成の効果を考えること。 | |||
| 記述 | ウ 事実と感想、意見などとを区別するとともに、目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いたりすること。エ 引用したり、図表やグラフなどを用いたりして、自分の考えが伝わるように書くこと。 | ウ 伝えたい事実や事柄について、自分の考えや気持ちを根拠を明確にして書くこと。 | ウ 事実や事柄、意見や心情が相手に効果的に伝わるように、説明や具体例を加えたり、描写を工夫したりして書くこと。 | イ 論理の展開を工夫し、資料を適切に引用するなどして、説得力のある文章を書くこと。 |
| 推敲 | オ 表現の効果などについて確かめたり工夫したりすること。 | |||
| 交流 | カ 書いたものを発表し合い、表現の仕方に着目して助言し合うこと。 | オ 書いた文章を互いに読み合い、題材のとらえ方や材料の用い方、根拠の明確さなどについて意見を述べたり、自分の表現の参考にしたりすること。 | オ 書いた文章を互いに読み合い、文章の構成や材料の活用の仕方などについて意見を述べたり助言をしたりして、自分の考えを広げること。 | エ 書いた文章を互いに読み合い、論理の展開の仕方や表現の仕方などについて評価して自分の表現に役立てるとともに、ものの見方や考え方を深めること。 |
| 言語活動例 | ア 経験したこと、想像したことなどを基に、詩や短歌、俳句をつくったり、物語や随筆などを書いたりすること。 | |||
| イ 図表などを用いた説明や記録の文章を書くこと。 | イ 多様な考えができる事柄について、立場を決めて意見を述べる文章を書くこと。 | イ 目的に応じて様々な文章などを集め、工夫して編集すること。 | ||
3
2011.7.27
山梨総合教育センター B 「書くこと」講習会
「珠玉の言の葉」 心に留めておきたい言葉を古典から探し紹介する文章を書く
学年 第3学年
古典から自分の心に留めておきたい言葉を探し、友達に紹介する文を書いて、お互いに交流・評価し、自分の表現に生かす。
(1)育成を目指す言語能力
- 古典の言葉や一節を用いて、簡単な文章を書く力。
- (紹介文、解説文、随筆、紀行文、感想文など)
- 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項
- (1)ア中3(イ)古典の一節を引用するなどして、古典に関する簡単な文章を書くこと。言語活動例中3
イ「目的に応じて様々な文章などを集め、工夫して編集すること」指導事項書くこと中3年
エ書いた文章を互いに読み合い、論理の展開の仕方や表現の仕方などについて評価して自分の表現に役立てるとともに、ものの見方や考え方を深めること。(2)単元設定の理由
義務教育最終年である中学校3年生が、古典や言葉についての学習をもう一度振り返り、今後の生活の中に生きる言葉の力について考える機会として設定した。(後略)〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の関連
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項の指導は3領域のいずれかの指導とかかわらせて行うことができるので、ここでは「書くこと」の指導事項に照らして具体化することを試みた。
画像
ア 取材
イ 記述
エ 交流 ウ 推敲
これまでの古典の学習を振り返り、心に残っている表現や和歌などをきっかけに、様々な古典に触れ、心に留めておきたい言葉を探す。図書館を利用して、できるだけ多種多様な文献に触れる。選んだ古典の一節や和歌について簡単な文章を書く。文章の種類(表現の特徴)や描写の仕方や比喩の用い方(表現の仕方)について、どのようにすれば効果的に紹介できるか考える。書き上げた作品をグループ内で観点をもとに読み合い、相互評価をする。文種がさまざまな点になることで、評価する観点が変わってくることも生徒自身に気づかせたい。グループ内の交流で友人と読み会い、相互評価することで気づいたことを参考にして、より相手に伝わりやすい、効果的な表現になるように推敲する。
〔古典の世界へ〕「心に留めておきたい言葉を探す」という学習課題を設定した。生徒自身が、友人や保護者、また自分自身の言葉によって勇気づけたり、心を動かされたりした経験は多くあるだろう。今後の生活においても、そのような言葉を自分でもち続けることで、言葉が実感できるときがくるものと考える。そのような言葉を探し、その時の状況を書き表させる。(後略)
4
2011.7.27
山梨総合教育センター B 「書くこと」講習会
(3) 指導上の工夫・ポイント
【五つの言語意識】
目的意識 今後の自分の人生において、自分が勇気付けられたり、心が動かされたりするような
言葉(表現)をもつために。(言葉の美しさを感じさせる表現、心に残った表現、口ずさみたくなる表現、尊敬する人物の言葉など)
相手意識 学級の友達に向けて
方法意識 既習の学習も生かして、古典の中からお気に入りの言葉を学校図書館で探し、それを様々な文種を通して書く。
場面状況意識 相手に自分が選んだ言葉のイメージが伝わるように工夫することを意識して書く。 評価意識 古典から選んだ言葉について、相手にイメージが伝わるように簡単な文章を書くこと ができたか。
【学習過程を意識させる】
書くことのプロセスを生徒に意識させるために、学習の流れを確認することができるようなワークシート(例:1枚ポートフォリオ)を使いたい。ワークシートの項目として、下記のような学習過程に沿った記述欄を設け、学習の目標を見失うことなく、1時間1時間の授業における学習の流れが確認できるようにする。
1 学習の目標を確認(学習課題の提示)既習事項やこれまでの言葉に対する経験なども確認
2 学習活動1 取材 学校図書館において言葉を探す
3 学習活動2 記述 言葉を紹介するためにふさわしい書き方について 4 学習活動3 交流 グループ内での読み比べを通して
5 学習活動4 推敲 グループ内交流を経て
6 自己評価 学習を通して身に付けることができた力とは
目標に対する自己評価 (最終評価欄)
・学習活動 1取材 2記述 3交流 4推敲 5発表 どこをどのように意識したか。 ・古典を学習しての感想、印象?
(4) 単元全体の指導計画(全6時間 伝国(1)2時間、書くこと3時間、伝国(2)書写1時間)
これまでの学習を振り返り、言葉を探す方法について考える。・学校図書館を利用して、取材する。 「喜怒哀楽」などの観点から絞り込んでいく。(例:「哀」であれば、自分が将来何かに失敗した時に、自分を勇気づけてくれそうな言葉。「楽」であれば、美しい情景に出会ったときに口ずさんでみたい和歌。など) |
5
2011.7.27
山梨総合教育センター B 「書くこと」講習会
| 1時 構成・記述 | 文章の形態を指し示すことで、生徒が考えを広げられるようにする。(例:小説形式。解説形式など)。 | |
| 第三次 | 1時 交流2時 推敲 | ・自分が書いたものをグループ内で発表し、お互いに評価し合う。3~4人グループを作り、グループ内発表を行う。作品を実際に紹介し、自分の作品に対して評価してもらう。評価の観点は、1文章形態 2構成 3記述の3点である。紹介する言葉に対する考えや思いがより効果的に伝わるために、どのような工夫があったのかについて、意見の交換を行う。・友人の意見をもとに文章を推敲する。グループ内交流を経て得た意見を参考に、自分の文章を推敲する。 |
| 書写 | ・色紙に自分が選んだ言葉を書き、発表する。 |
(5) 本時 ( 三次の第1時) 1 本時の展開
| 指導内容 | 学習内容・活動 | ||
| 課 題 の 提 示 ・ 意 欲 付 け | ・それぞれが書いた作品を交流し、お互いに評価しあうことを伝える。「友人がどのような言葉を探し、どのように紹介するのか。お互いに評価しあうことで、自分作品をさらによくするためのヒントを得よう」(目的・相手・方法・場面・評価の五つ言語意識を確認する。)・評価する観点を確認させる。 1 文章形態 友人に伝えるために効果的な文章形態・構成になっているか。 2 構成 読み手を意識し、わかりやすい文章形態となっているか。読み手を引きつける文章構成になっているか。3記述 描写の仕方や比喩の用い方など表現の仕方が工夫されているか。文章的に間違っているところやわかりにくい表現はないか。 | ・本時のねらいを把握する。 古典から選んだ言葉をどのような文章で紹介するのか。紹介するに当たって、友人からよい点を学んだり、さらによくするためにはどうすればよい共に考えたりする。・友人の作品を評価するために3つの評価観点を確認する。・どのようにアドバイスをすれば、友人に評価が適切に伝えられるか考える。 | ・「書くこと」の援護活動を通して、伝統的な言語文化に関する事項の指導をすることを意識させる。・特に指導と評価の一体化を指導者が意識して指導に当たるようにする。・共に考え作品をよりよいものに仕上げていこうという姿勢を確認させる。・さまざまな文章形態で言葉を紹介していることが考えられる。それぞれの文章形態にどのような評価が必要なのか考えさせる。 |
6
2011.7.27
山梨総合教育センター B 「書くこと」講習会
・文学的文章形式作品・説明的文章形式の作品 | ・さらに作品をよくするためには、(相手に効果的に伝えるためには、)どのような工夫が考えられるかアドバイスする。1 3~4人のグループを作り、一人ずつ発表していく。2 発表を聞きながら、評価観点に基づき、ワークシートに気づいた点などをメモしていく。発表後、メモを参考に意見交流を行う。 | ||
・友人の作品からまなんだこと・アドバイスしてもらったこと・交流をすることで得た視点など | ・友人の作品から学んだこと、アドバイスしてもらったこと、またアドバイスしたことを振り返り、自分の作品にどのように生かすか考える。 |
る
2 交流の観点
1 文章形態 友人に伝えるために効果的な文章形態・構成になっているか。
2 構成 読み手を意識し、わかりやすい文章形態となっているか。読み手を引きつ
ける文章構成になっているか。
3 記述 描写の仕方や比喩の用い方など表現の仕方が工夫されているか。文章的に
間違っているところやわかりにくい表現はないか。
3 本時の評価
画像
画像
画像
1) 言語についての知識・理解・技能
画像
- 評価規準=交流を通して、古典から選んだ言葉が効果的に紹介できるように観点に基づき作品を評価している。
- 十分に満足できる状況の具体例=交流を通して、古典から選んだ言葉が効果的に紹介できるように観点に基づき作品を評価している。また、作品の文章形態によって評価の仕方が変わることを理解し、評価に生かしている。
- C と判断される生徒への手だて
- 交流の観点について、他のグループのメモなどを参考にさせながら確認する。
- 友人と交流したことを評価メモに記述させることで交流に慣れさせる。
- 評価規準=作品をさらに効果的にするために、評価観点を基にグループ内で意見や感想を交流させようとしている。
- 十分満足のできる状況の具体例=作品を評価観点を基に適切に評価し、積極的に意見を交流している。
- C と判断される生徒への手だて
- 教師が具体的に評価例を示し、観点ごとに感想をワークシートに記入させる。
画像
画像
画像
2) 国語への関心・意欲・態度
画像
7
2011.7.27
山梨総合教育センター B 「書くこと」講習会
(6) 単元の評価
【言語についての知識・理解・技能】
・評価規準=古典から自分に投げかける言葉を探し、その言葉を友人に紹介するために交流を
通してお互いの作品を評価し、自分の作品に生かすことができる。
・十分満足のできる状況の具体例=古典から自分の心に留めておきたい言葉を探し、その言葉
を友人に効果的に紹介するために交流を通して、評価観点に基づき積極的に作品を評価し、
自分の作品に生かすことができる。・C と判断される生徒への手だて
(後略)
河野庸介・佐藤喜美子 編著 「中学校国語科新授業モデル 伝統的な言語文化を国語の特質 に関する事項編」 明治図書 2011
【資料1】 ポートフォリオ例
○これまでの経験から生徒自身が勇気づけられたり、励まされたり、心動かされた言葉についてもう一度想起させ、新しい言葉をもちたいという意欲を喚起する。○教師側で名言集などの参考資料を提示し、それを糸口に言葉を考えさせる。○友人の作品を紹介し、自分が選んだ言葉を紹介させるのであれば、どのような文章表現を選ぶか考えさせる。○交流の評価観点を再確認させ、感想を述べるところからはじめさせる。○ワークシートを振り返らせて、学習の流れを再確認させる。
画像
8
2011.7.27
山梨総合教育センター B 「書くこと」講習会
【資料2】
9
2011.7.27
山梨総合教育センター B 「書くこと」講習会
【資料3】
10
2011.7.27
山梨総合教育センター B 「書くこと」講習会
【資料2】【資料3】【資料4】【資料5】
11


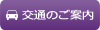



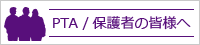

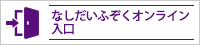

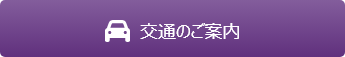
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp