ワールド・カフェの活用
ワールド・カフェの活用 ~交流で自分の考えを広げ、深める~
山梨大学教育人間科学部附属中学校
望月陵(もちづきりょう)
キーワード 言語活動 交流 ワールド・カフェ ファシリテーション
概要 ・交流の工夫によって,自分の考えを深め広げる。
・ワールド・カフェを教室版での文学的文章の読解。
1.効果的な交流を
「言語活動を通して知識技能を活用させ、思考力・判断力・表現力等を育むための手立て」
言語活動の充実が求められる中、「話し合い」や「交流」などの活動を意図的に学習過程に組み込む場面を多く設定している。小グループによる意見交換は効果的であることが実感としてある。しかし、ただの意見発表で終わってしまったり、深みや広がりをもった交流にまでたどり着かなかったりする場合も多く見受けられる。そこで、効果的な交流のあり方の一つとして、山梨大学の須貝千里教授とともにファシリテーション(facilitation:集団による知的相互作用を促進する働き)のひとつとして「ワールド・カフェ」の教室版に取り組んだ。
ここでの目標は、以下の通りである。
- もっている知識や考えなどを活用する。
- 友人と関わることで自分の考えを形成する。
- 積極的な学習への参加意欲。
2.ワールド・カフェとは
| 「ワールド・カフェ」 ワールド・カフェは1995年にアニータ・ブラウンとディビッド・アイザックスによって始められました。メンバーの組合せを変えながら、4〜5人単位の小グループで話し合いを続けることにより、あたかも参加者全員が話し合っているような効果が得られる会話の手法です。その名が示すようにカフェのような、リラックスした肩の凝らない雰囲気ができやすいことから、プロジェクトやチームの、様々な利害関係者の新しい関係作りを進めていきたい場面などに使われることも多いようです。 (香取一昭・大川恒 著「ワールド・カフェをやろう!」より) |
3.ワールド・カフェ教室版に
前述の通り、ワールド・カフェ形式で行うと2時間ほどかかる。そこで、1単位時間(50分)で収まるワールド・カフェ教室版に改訂した。
①1単位時間で行うための時間設定
| 学習活動 | 時間 | 活動の概要 | |
| 1 | 課題の確認 | 5分 | ・本時の課題を確認する。(ワールド・カフェに適した課題設定が求められる。今後の課題でもある。) |
| 2 | 第1ラウンド | 10分(移動1分) | ・4人1グループで第1ラウンド。 ・第2ラウンドに向かう際にカフェ・ホスト(1名)を決め、ホストはその場に残る。 ・ホスト以外の3名は、新たな視点を得るため(必ずお土産を持って帰るように伝える)に他グループに旅立つ。 |
| 3 | 第2ラウンド | 12分(移動2分) | ・新たなグループで第2ラウンド。 ・カフェ・ホストは、グループで話し合われたことを他グループからの旅人に説明する。 ・第3ラウンドは、第1ラウンドと同じメンバー。 ・第1グループに帰りながら、他グループのシートを見ながら、意見交流を行う。 |
| 4 | 第3ラウンド | 10分 | ・カフェ・ホストが中心となり、さまざまな視点を基に、課題解決のための集約に入る。 ・課題に対して、まとめることができなくてもよい。 |
| 5 | 全体交流 | 10分 | ・各グループで話し合われたことを発表する。 ・自分の考えを振り返りシート等に記入。 |
②生徒の自由な発想を
- 落書き用模造紙の利用
各グループに思いついたことや考えたことを書き残すための「落書きシート(模造紙大1枚)を用意した。また、太めのカラーペン(今回はプロッキー)を一人一本持たせた。
綺麗にまとめるためのものではなく、生徒の思いつきや現時点での考えを気軽に表出させることが目的である。
- 全体共有の場面
全グループに交流の概要を発表させる。どのような形でまとめていくかは、教師の裁量。
③リラックスした環境作り
- ラウンド終了の合図
大声で「やめてください」というのも雰囲気が壊れるので、時間になったら教師が挙手をする。それに気がついた生徒も挙手をし黙るルールを確認すれば、スムーズな進行が可能になる。
- 図書室が理想的
4人で囲み、落書き用の模造紙が広げられる大きさのテーブルがあるといい。本校図書室には適度な大きさのテーブルや提示用のプロジェクターなどもあり、有効活用した。教室でも4人分の机を合わせることによって可能になるが、机の高さが違ったり、ちょっとした隙間が落書きをするときのストレスになったりすることがある。
【実践例】附属中学校 中等教育研究会
「少年の日の思い出」をワールド・カフェで読む。
1 指導の目標
【関心・意欲・態度】
紹介する文章の内容に関心をもち、自分の考えを明確にするために、友人と考えを交流しようとする。
【指導事項 読むこと 中1】
Cオ 文章に表れているものの見方や考え方をとらえ、自分のものの見方や考え方を広くすることができる。
(Cウ場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み、内容の理解に役立てることができる。)
【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】
(1)イ中1(イ)語句の辞書的な意味と文脈上の意味との関係に注意して読むことができる。
2 指導計画と評価計画(C領域「読むこと」53時間中の6時間)
(1)評価規準
| 国語への関心・意欲・態度 | 読む能力 | 言語について知識・理解・技能 |
| ①文章に関心をもち、自分の考えを明確にするために、友人と考えを交流しようとしている。 | ①文章に表れているものの見方や考え方をとらえ、友人との交流を通して、自分のものの見方や考え方を広げている。(オ)②登場人物の心情や行動、情景描写、物語の構造に注意して読み、内容の理解を深めている。(ウ) | ①語句の文脈上の意味をとらえ、それが文章の中で果たしている役割を考えながら読んでいる((1)イ(イ)) |
(2)学習過程の概要
| 単元(教材)名 | ( ヘルマン・ヘッセ「少年の日の思い出」 ) 〈 6時間計画 〉 | |||||
| 言語活動例 | ウ 課題に沿って本を読み、必要に応じて引用して紹介すること。 | |||||
| 指導事項 | 重点 | 学 習 活 動 | 評 価 規 準 | 時 | ||
| ア | 【語句の意味の理解】 文脈の中における語句の意味を的確にとらえ、理解すること。 | 「少年の日の思い出」を読む。(事前)新出漢字や難語句について調べる。 | 関①課題を解決するために、積極的に「少年の日の思い出」を読もうとしている。 | 1 | ||
| ウ | 【文章の解釈】 場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み、内容の理解に役立てること。 | 現在の場面と回想の場面の構成や登場人物の描写に注意しながら展開をとらえ、内容を理解する。 | 読②言①文章中の言葉を根拠として引用し、 さまざまな観点から描写の効果について考えている。 | 23 | ||
| エ | 【自分の考えの形成】 文章の構成や展開、表現の特徴について、自分の考えをもつこと。 | ○ | 内容の理解を深めるために、展開や表現の特徴などについて友人と考えを交流する。 | 読②根拠を本文中より探し、自分の考えを整理している。 | 45 | |
| オ | 【自分の考えの形成】 文章に表れているものの見方や考え方をとらえ、自分のものの見方や考え方を広くすること。 | ◎ | グループで交流を基に、ポートフォリオにまとめることで、自分の考えを明確にする。 | 読①紹介するために、本文中の言葉を根拠として考えている。 | 6 | |
| カ | 【読書と情報活用】 文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け、目的に応じて必要な情報を読み取ること。 | |||||
| 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕 | (1)イ(イ)語句の辞書的な意味と文脈上の意味との関係に注意して読むことができる。 | |||||
(3)指導計画と評価計画
指導計画(読むこと 6/65時間 )
| 学習活動 | ||
| 事前 | ○新出漢字、新出音訓については事前学習。 | |
| 第一次 | 1時課題設定 | ○学習の目的を知り、学習過程を確認させる。 ○文章全体を通読し、話の展開や内容の大体をつかむ。 ・印象に残った場面について感想を残す。 |
| 第二次 | 2、3時語句の意味の理解文章の解釈 | ○描写に注意しながら場面の展開をとらえ、内容を理解する。 ・登場人物の心情変化・場面の構成【課題】 ・登場人物はどのような人物か。 ・「ぼく」は何をしたのか。 ・「ぼく」が一つ一つ潰したものは何か。・表現にどのような効果があるか。(明暗など) |
| 第三次 | 4、5時自分の考えの形成 | ○自分の考えを明確にするために、ワールド・カフェで交流する。【課題】前半部と後半部を比較してどのようなことがわかるのか。 ・「客」はなぜ少年時代の出来事を語ったのか。 |
| 第四次 | 6時 | ○交流を基に自分の考えをまとめる。 ・これまでの交流を参考に、自分の考えをポートフォリオに記入する。 |
3 本時の展開
(1)日時 平成23年10月22日(土) 10時20分 – 11時10分
(2)場所 山梨大学教育人間科学部附属中学校 図書室
(3)目標 グループで交流し、多くの考えに触れると共に、自分の考えを明確にすることができる。
(4)展開
| 学習活動 | 指導上の留意点 | 評価について | |
| つかむ | 1.これまでの学習を振り返り、本時の目標を知る。 ・前時までの学習を確認する。 前半部と後半部を比較して、どのようなことがわかるのか。 | ・これまでの課題に対する学習感想などを紹介する。 | |
| 深める | 2.前提について確認する。 ・物語全体の額縁構造 ・「僕」の情熱 ・エーミールという人物 ・「僕」が潰したもの | ・これまでの学習課題から前提となる部分の確認を簡単に行う。 | ・観点を基に作品について考え、意見を述べているか。【読①】 |
| 3.課題についてグループで交流する。 ・第1ラウンド 10分 各グループでテーマを確認するとともに、課題解決について話し合う。 ・第2ラウンド 10分 カフェ・ホストを残して、他の3人は旅に出る。他で新しいグループを形成し、話し合う。 ・第3ラウンド 10分 各グループでメンバーが持ち帰った考えを基に交流を行い、グループとして考えをまとめる。 | ・自分の考えと根拠を明確にさせる。 ・カフェ・ホストの役割を確認する。 ・生徒が進行役となり、グループで検討させる。 ・学級全体で各グループの考えを交流させる。 | ・観点を基に積極的に交流しているか。【関①】 | |
| 一般化 | 4.自分の考えをまとめる。 ・交流を終えて、ポートフォリオに自分の考えをまとめさせる。 | ・何人かに発表させ、成果と課題を明確にさせる。 ・本時の学習感想を記入させる。 | ・自分なりの考え方をまとめているか。【読①】 |
| 5.学習のまとめ ・身に付けた力をどのように生かすか考える。 | ・日常的な読書や今後の教材についても、今日の読みが生かせることを確認する。 |
4.実践を終えて
ワールド・カフェ教室版は、生徒にとって興味深い学習活動となり、意欲的に話し合う姿が見られた。要因として、普段あまり話さない人間関係の中でも、リラックスした状態での話し合いにより、それぞれが自分の意見を出しやすい環境にあることが考えられる。また、出てきた意見が生徒にとって斬新であり、お互いの考えを刺激し合うことができたものと思われる。このように意欲を喚起する場面では、大きな効果を得ることができたが、学習内容を広げ、深めるという段階にもっていくまでには、教師の力が必要であろうと思われる場面も見られた。以下に成果と課題を挙げる。
【成果】
- 話し合いが活発に行われる。普段、意見を言えない生徒も発表していた。
- 聞いてきた意見も自分の意見として発表しやすい。
- 考えを可視化(考えの深さは考えず)することで全員が参加できる。
- 4人を入れ替えることで対話が苦手な生徒にも教育手法として効果的な部分がある。
- 他教科においても活用することが可能。
【課題】
- ワールド・カフェに対応した適切な課題設定。
生徒同士での話し合いとなるので、生徒がこれまで獲得した知識や技能を活用し、自ら発見することができる課題を考えていきたい。 - 全体での考えの共有
学習内容の深化を生徒の交流だけですすめることは難しく、効果的な教師の指示や全体でのとりまとめが必要になる。 - さまざまな場面での交流の設定
生徒がワールド・カフェ自体に慣れるとさらに効率よい活動になると考えられる。 - 評価の検討
全体でのとりまとめももちろんだが、活動中の生徒の様子を以下にみとるか。活動中の評価規準やチェックシートの工夫などが今後求められる。
5.追記
他の教材や総合的な学習、学活などにおいてもワールド・カフェ形式の意見交流を行った。生徒は徐々に慣れ、友人と共に考えを練り上げることに興味を抱くようになった。また、自分の考えを形成することに対する視点を持つことができるようになったものと考えられる。
ラウンドの時間をさらに短くしたり、ラウンドの回数を増やしたりするワールド・カフェを「ミニ・ワールド・カフェ(=ミニ・カフェ)」と称して課題と機会をみながら積極的に取り入れている。今後、さらに改良加え、機会を積み重ねることで内容の充実を図りたい。
【参考文献】
冨山哲也編著「<単元構想表>でつくる! 中学校新国語科授業STARTBOOK」明治図書 2011
河野庸介編著「中学校国語科新授業モデル」(読むこと編)明治図書 2011
井上尚美 「思考力育成への方略 —メタ認知・自己学習・言語理論—」 明治図書2007
香取一昭 大川恒 「ワールド・カフェをやろう!」 日本経済新聞社 2009
堀公俊 「ファシリテーション入門」日本経済新聞社 2004


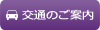



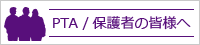

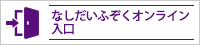

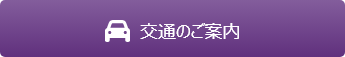
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp