ホーム 教育研究 山梨大学若桐講座 第4回山梨大学若桐講座 2013年8月31日(土)
第4回山梨大学若桐講座 2013年8月31日(土)
附属中学校生徒のための山梨大学若桐講座
4年目となりました若桐講座です。本年度はさらに講座数も増えて準備していただき、附属中生徒の成長を願う特別授業が実施されました。
第4回「山梨大学若桐講座」を8月31日(土)に開催しました。生徒達の夢と可能性がさらに広がり、知識が深まることの期待が少し実現できたかなと思います。
魅力的な10の授業
授業1) 「英語学習と私たち」 古家貴雄 先生
① 日本人にとって英語とはどのような言語なのか?
・英語学習に対しての見方や考え方が変わったことが多かった。学習方法の見直しにもつながった。(生徒)
・わかりやすく楽しく話を聞くことができました。目標を持ち、継続して英語を勉強することが大切だということがわかりました。これからまた英語を勉強してみようかと思いました。ありがとうございました。(保護者)
授業2)「権利を主張することの意義」 森元拓 先生
「自己の権利を主張する」ことの社会的意義について、法学的観点から考察する。
・権利についてよく分かりました。これからの日常生活でも権利についてよく考えていきたいです。そして権利を主張することの大切さも分かりました。ありがとうございました。(生徒)
・多数決で正しいことがでてくるか、多数決で決めて良いのか。世間一般の多数が本当に正義なのか。多数決というのは間違えやすい、危険性がある。という理論がとても参考になった。少人数で先生との距離も近く、わかりやすくて大変濃い講義でした。(保護者)
授業3)「数学の活用」 清野辰彦 先生
現実事象の問題を数学を活用して解明したり、問題解決したりする過程を味わうとともに、その内容について説明いたします。また、その内容では、フィボナッチ数、黄金数等、不思議な数についても触れていきます。実際に、問題を解いていただきながら、進めていきます。
・ひまわりで数学することが最初はとても意外でした。ひまわりの種の並びが美しいという理由は数学にあったなんてとても感動的でした。ひまわり以外にも地球には数学があふれているんだろうと思うと、とてもうれしく思います。とても充実した90分でした。とても楽しかったです。ありがとうございました。(生徒)
・普段、理数の思考に無縁(?!)の生活を送っていますので数のマジックに出会えたような感覚でした。いつも使わない脳をフル回転させながら不思議さを楽しみながら受講することができました。ありがとうございました。数学って美しいなと思いました。今日の講義を好奇心旺盛に受けている息子の姿も頼もしく思いました。(保護者)
授業4)「絵や彫刻はなぜ動かないのか?」 村松俊夫 先生
ミレーの絵画「種をまく人」やロダンの彫刻「考える人」は動きません。それは芸術作品だから……。
・とても楽しい授業でした。私が生活する中ではとても発見できないようなものがたくさんあり、おもしろかったです。これからもいろいろなことに取り組んでみたいです。(生徒)
・とても分かりやすく説明して下さって子供達も楽しめていると感じました。(保護者)
授業5)「睡眠と呼吸 ~あなたは眠れていない~」 杉山剛 先生
「朝起きてもすっきりしない」、「日中すぐ眠くなる」、「朝起きると喉が痛い」、「いびきがうるさいと言われる」などの症状がある方はいませんか? これらは「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という病気の症状です。本講義では、「鼾の恐ろしさ」「寝だめは本当に有効?」「ナポレオンは本当に3時間しか眠らなかったの?」「昼寝、居眠りは悪いこと?」「テスト前日の徹夜勉強ってどうなの?」などの睡眠についての身近な疑問についてわかりやすく解説し、無呼吸の恐ろしさ(体への影響)を医療機器を使って実体験してもらいます。
・とても分かりやすくて昼寝や睡眠時間のことはとても参考になりました。また先生の話は本当におもしろくて、とても楽しかったです。(生徒)
・ユーモアに富み、子供にも大人にも分かりやすく楽しい授業でした。時代背景をつかんだ話し方や、講義内容で子供達が真剣に聞いていたのが印象的でした。(保護者)
授業6)「食事・睡眠とメンタルヘルス」 神澤尚利 先生
食事や睡眠といった生活習慣とメンタルヘルスとの関連について講義をする。特に、家庭や学校の環境や対人関係によりストレスを感じやすい、多感な思春期・青年期において生活習慣とメンタルヘルスがどのように関連しているのかという話題を中心に解説し、対策を検討する。
・グラフや表にまとめてあって理解しやすかった。運動をしている人としていない人で違いがあったり、ほとんど変わらなかったり、初めて知ったことがたくさんあって興味が持てました。(生徒)
・睡眠食事が基本的に大切だとは思っていましたが、精神面にも影響することを知り、人の体の繊細さを知りました。ブレインストーミングにはとても興味を持ちました。機会があればもっと詳しく学びたいです。(保護者)
授業7)「地震と付き合う」 杉山俊幸 先生
自然災害概論、地震発生のメカニズム、地盤構造や地形と地震動の関係、地震と津波、耐震・制振・免震の違い、振動を抑える機構、ソフト面からの防災技術。講義は、机上実験(私自身が受講者の皆さんに示しながら実施します)を交えながら進めます。
・普段考えなかった事も深く追求すると、とても興味深くおもしろいものになった。とても良い授業で実験も楽しかったです。また行きたいです。(生徒)
・大変勉強になりました。このほうな機会を本当にありがとうございました。中学生にもわかりやすくする工夫がなされていて、先生の気持ちの暖かさが伝わってきました。(保護者)
授業8)「ごみから考える環境問題」 金子栄廣 先生
ごみに関する基礎知識、環境対策の状況、市民としてできること。
・日常生活の中で行っている行為、認識していた事意外にも人間の生活は環境への影響が大きいなと感じました。ゴミの処分までの流れがよく分かりました。山梨県内での状況、身近な活動を知ることができたのでよかったです。説明がとても明確で分かりやすかったので集中して受講できました。(生徒)
・私たちの日々の生活に密着したゴミ問題ですので、まじめに取り組み解りやすく授業して下さいました。さらなる取り組み(3R)をして行きたいと思います。(保護者)
授業9)「水の生き物と私たちの暮らしとの関わり」 岩田智也 先生
私たちは毎日を普通に生活するだけで、自然界に影響を与えています。食事をしたり、お風呂に入ったりといった普段の行動が、多くの生き物が暮らす川や湖、そして海の環境をも変えているのです。しかし、多くの人はこのことに気づかないまま暮らしています。そこで今回の講座では、講義と簡単な実験を通じて私たちの身近な暮らしと生き物との関係を探り、川や湖、海の生き物を保全するために必要なことを考えてみたいと思います。
・今回の授業を通して知った事がたくさんあり川のことを良く分かったので良かったです。また機会があったら川などに行ってみたいと思いました。(生徒)
・とても分かりやすく、子供達の理解もより深まったものだったと思います。水道について思いの外、甲府の水の汚れに驚きました。ありがとうございました。(保護者)
授業10)「世界の食糧生産と環境」 新藤純子 先生
世界の食糧生産の変遷と現状を理解し、環境と農業の関わりについて考える。
・知らない言葉が出てきたりしたが歴史などを振り返りながら受けたのでどのような言葉であるのか分かった。食料生産と環境が関係していることをはじめて知った。初めて学んだことばかりだったので楽しかった。肥料とはどんなものなのか考えることが出来て良かった。(生徒)
・1950年頃より肥料の開発によって飛躍的に作物の生産量が増えたことを知った。また2050年人口90億人見込みでの食料も今の技術では確保が可能であることに興味を感じました。(保護者)












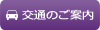



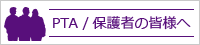

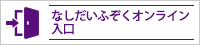

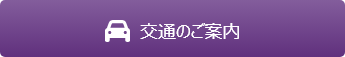
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp