平成22年度 保健体育科研究主題 「学習内容の明確化・構造化を目指した授業の創造」
保健体育科研究主題
「学習内容の明確化・構造化を目指した授業の創造」
飯塚誠吾・秋山知洋・川久保愛
1.主題設定の理由
本校の保健体育科では、平成19年度から「学習内容の明確化」を目標に研究を進めてきた。本年度は、これまで課題となっていた体育の目的の具体的内容(すべての子どもたちが身につけるべきもの)「技能≒身体能力」「態度」「知識、思考・判断」を身につけさせ、一定の「経験」をさせることや、新学習指導要領で謳われている指導内容と照らし合わせてみて、本校でまとめている「学習内容」が妥当であるかどうかを検証しながら、追加や修正・訂正をしていく必要があると考えている。また、すべての領域について学習内容を明確化し、それらを整理して構造化する必要があると考え、研究テーマを設定した。※注:本校保健体育科が目指す構造化とは、学習内容の体系化【基礎的・基本的な内容のつながり(広がり)≒横軸の関連性】と系統化【応用的な内容のつながり(深まり)≒縦軸の関連性】を両面からとらえて示すものとする。
また、新学習指導要領が公示され、本校でも平成24年完全実施に向けて移行措置に取り組んでいる。平成24年度には時間数が105時間に増加し、学習内容においても1・2年生を通じて選択であった「武道」「ダンス」を含めて、すべての内容を必修とすること、3年生では、「体つくり運動」「体育理論」を除き、選択とすること、「球技」について「ゴール型」「ネット型」「ベースボール型」として類型で規定すること、となった。さらに、発達段階においても小学校・中学校・高等学校において、より一層の連携が図られるよう小学1~4年生、小学5年生~中学2年生、中学3年生~高校3年生といった4年間を1つの枠とした考え方も示された。これにより、中学校では小学校との連携及び高等学校との連携を視野に入れた指導が求められてくる。そこで本校では、附属小学校との連携を深めながら「学習内容の明確化・構造化」を研究テーマにし、研究を進めていきたいと考えている。
2.研究の目的
中央教育審議会答申では、保健体育科の課題として、①運動する子どもとそうでない子どもの二極化傾向にある。②子どもの体力低下傾向が依然深刻である。③生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成が十分に図られていない例も見られる。④学習体験のないまま領域を選択していることが見られる。ということが示された。本校の現状を見てみると、特に①・②の傾向が見られる。①については、休み時間や学校外の時間に、外で遊んだり地域の行事(子どもクラブの球技大会など)に参加するなど、運動や体を動かす時間の少ない生徒の割合が多いことが原因の一つと考えられる。②については、昨年度の体力テストの結果から、「反復横とび」「ハンドボール投げ」「持久走」の3種目で全国平均を下回るデータが見られる。
新学習指導要領の目標の中に「運動を適切に行うことによって、体力を高め心身の調和的発達を図る」「運動における競争や協同の経験を通して、公正に取り組む、互いに協力する、自己の役割を果たすなどの意欲を育てるとともに、健康・安全に留意し自己の最善を尽くして運動をする態度を育てる」ということが明記されている。このことから、保健体育科では「学習内容の構造化」を図り、生徒一人一人に運動や健康・安全についての理解と運動の合理的実践を通して、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進のための実践力の育成と体力向上を図り、明るく豊かな生活を営む態度を育てることを目標に、多くの領域を体験し、様々な動きを身に付ける時期、生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現するための資質や能力を身につける時期といったことを考慮し学習内容の構造化を図っていくことを目的とする。これらのことを受け、保健体育科では次のような生徒像を目指し、研究実践を行うこととする。
| 保健体育科として目指す生徒像○運動の楽しさやできる喜びを実感することができる生徒○探求心をもって誠実に学ぶことができる生徒○互いの良さを認め、豊かなかかわりが体験できる生徒 |
3.全体研究とのかかわり
全体研究では、『知の再構成を目指して~「かかわり」を生かした学習過程の工夫~』をテーマに3年計画の最終年次をむかえ、昨年度同様研究のポイントとして以下のように設定した。
- 「かかわり」(学習内容の関連性)を生かした学習課題・活動の設定
- 伝える学習活動
- 学びの評価
これらを各教科の目標やねらいと生徒の実態に組み合わせることで、学習内容の「かかわり」を意識できると考えている。そこで保健体育科では、次のようにとらえ全体研究と関わりを持たせていきたいと考えた。
①「かかわり」(学習内容の関連性)を生かした学習課題・活動の設定
体育では身体の動かし方や姿勢の取り方で深い関わりがある技能が少なくない。例えば、1年次に行う器械運動の中のマット運動の倒立の姿勢では、安定した姿勢を取らせるため身体を直線的に伸ばしバランスの取りやすい姿勢を取らせる。そのときのポイントとして視線を意識させる。人間の身体は、構造的に下を向けば背中が丸まり腰が曲がる。しかし、視線を上に向ければ背筋が伸び腰も伸びる。この姿勢(技能)を身に付けるために時間をかけ指導を行う。2年次に行う水泳の背泳ぎの授業でも、まずは仰向けに浮くことから始めなければ先に進めない。その姿勢は倒立とほぼ同じ姿勢である。浮力(水からの圧力)を得るために直線的に伸びた姿勢を取らせる。その姿勢を指導するためには時間がかかることが予想されるが、マット運動で行った視線を意識させればすぐに直線的な姿勢を取ることができる。1つの例であるが、学習内容の関連性「かかわり」を意識させる学習内容につながってくる。その他にも体育の授業の中で運動するために最も大事な「母指球加重」に関しても体重移動や力強い動きをする上でも様々な動きに関わる動作だと言えます。
また、毎時間の授業において、核(コア)となる学習内容を明確にする。例えば、球技のゴール型の「ゴール前のスペースに走り込むこと」を学習する授業では、『空間(スペース)を認識し、ゴール前の空いている空間(スペース)を見つけ出し移動すること』が学習の中心となるが、それを学ぶには「相手ディフェンスの位置」「入るタイミング」「スピード」「フェイキング」などの様々な要素が関連してくる。そこで、それらの要素を加味し工夫したゲーム(ルールや場所、用具などを考慮)を取り入れることで、教科での学習内容の「かかわり」を生かした活動が行えると考えている。
②伝える学習活動
単元や種目に合わせた学習カードを作成し、授業のポイントだけでなく、学んだこと、発見したこと、悩んだこと、つまずいたことなどより具体的に書かせることで、1時間の学習で身につけたものを表現できるようにしていきたい。さらに昨年度の課題を踏まえて、「共に活動する仲間に指示やアドバイスができる場面」や「コミュニケーションを通して新たな視点に気付く場面」をつくっていきたいと考えている。このことについては、仲間の技能・表現に対して簡単な言葉で「うまい」「ナイス○○」「今の良かったよ」など情意面によるもの、一方では教師が視点を持って指導する中で「今の○○が良かったよ」「もう少し○○した方がいいね」といった簡単な言葉がけにより、その技能に対する善し悪しの認知と理解が深まり、お互いに評価しあえる活動を仕組んでいきたいと考えている。また、グループでの作戦の中でお互いに意見(情報)交換をし、子どもたちが伝え合う活動を通して個人技能・集団技能の習得がより確実なものになったり、技能をより向上させたりすることができると考えている。
この活動をより効果的に行うためには、教師がポイントとなる視点をきちんと与え、種目ごとの基本用語や分かりやすい言葉で説明ができるように助言する必要があるので、その点にも十分配慮した授業づくりを行っていきたいと考えている。
③学びの評価
学習カードに1時間ごとに学習の成果や課題をより具体的に記述することで、これまでの学習の振り返り(変容や学習の成果)が確認できるようにしていきたい。また、各授業の後半でゲーム的な要素を取り入れることで、「学んだことを生かした動きや技ができているか」や「既習のものから選んだり、複数の要素を合わせたりしているか」などを評価につなげていきたいと考えている。さらに、上記②の内容については、「ポイントとなる内容を理解した説明や発言をしているか」「様々な角度から捉えているか」「説明が分かりやすいか(伝わっているか)」などを評価したり指摘したりできるような活動を取り入れ、学びの様子が見取れるようにしていきたいと考えている。
4.今年度の研究内容と課題
昨年度の公開研究会では、水泳について、学習内容の明確化およびそれに伴う評価規準の作成を行った。新学習指導要領が提示され、指導すべき内容が具体的に示されたことを受け、本校でも教えるべき内容(学習内容)を精選して授業を行った。授業後の分科会では、まず、本校の研究テーマの柱となる『かかわり』に関連する活動について多くの意見が交わされた。「学んだことを伝える活動」について、生徒同士で技能に関わるアドバイスや解説をしたり、意見交換ができたりするような場面を学習内容に応じて設定していく必要があるとのご意見を頂いた。また、生徒の実態に応じた技(技術)を取り扱うことも学習内容を習得させる上で大事なポイントであるとのご意見も頂いた。
そこで本校保健体育科は、今年度も「技能」という観点に焦点を当てながら『学習指導内容・計画の見直し、それを整理して構造化する』一方で、本校の研究テーマの「かかわり」に関連する活動についても研究を進めていきたいと考えている。
さらに、小中の連携についても教師が交流できる機会を増やし、他の小中学校に発信できるような取り組みを行っていきたいと考えている。具体的には以下の3点を挙げた。
①『基礎的・基本的な技能』、『基礎的・基本的な技能を活用する、使いこなせること(既習の内容を変化させる、相手や状況に合わせて使うなど)』についての学習内容の構造化を行う。
『基礎的・基本的な技能』について、その種目(運動)のメカニズムから、「基礎・基本」となる運動の内容を洗い出し、その運動の本質的な内容(より良く体を動かすための体の使い方や各々の技能の基となる体の動き)の精選を行う。「活用すること」においては、「基礎的・基本的な技能」に基づいて、より高度な試合(ゲーム)を行うために必要とされるポイントやこつを洗い出し、関連性を図りながら構造化を行う。
②『種目の特性と技能』のかかわりを明確にする。
集団の実態に合わせたルールの考案や簡易ゲームの適用、場の工夫、各個人の技能や関心を生かした戦術、相手の実態に応じた作戦など、これまでに習得した技能を状況に応じて活用できるように、その種目の特性や技術同士との関連性(かかわり)を意識させることで、知の再構成を目指していきたい。さらに、仲間同士で技術の解説やアドバイスができるような場面の設定をしていきたい。
③小・中の連携を図る。
本校は、附属小学校から入学してくる生徒が4分の3を占めているため、小学校との連携を図り、小学校での発達段階に応じた運動技能を確認できれば、中学校で教えるべき学習内容がより明確になり、学習効果が一層高まると考えた。今年度はこれまでの情報交換や授業観察だけでなく、ゲストティーチャーとして附属小の授業を行うなど、より連携を図っていきたい。
5.研究計画
○1年次・・・学習内容の明確化・構造化
○2年次・・・学習内容の明確化・構造化+「学んだことを伝える活動」「学びを見取る活動」に
関わる研究
○3年次・・・研究の検証とまとめ
①本校の保健体育科でどのような特色を盛り込んでいくのかを考えながら、第1・2学年の必修教科について年間の指導計画を作成する。また、第3学年における選択制授業について選択する領域での種目の検討及び年間の指導計画の作成を行う。
②年間指導計画に位置づけられた各教材同士のつながりと生徒の発達段階を意識しての「運動・技能の内容」を中心に構造化を図る。
③構造化した学習内容をつながりや関連性、特に指導の重点や特色が明確になるような整理方法の工夫を行う。
④指導と評価の一体化を目指した学習内容に対する評価規準の見直しを行う。
この際、特に②の段階で生徒がその教材の特性に触れ、楽しさや喜びを感じ、後の実践につながって欲しいという願いを基本とした「学習内容の重点化(特色を出す指導)」を考えられるように心がけたい。
6.昨年度までの研究の成果と課題
本校保健体育科は、昨年度から「技能」という観点に焦点を当てながら『学習指導内容を見直し、より精選・整理して改善する』ことで、学習内容をより明確にした授業づくりができると考えて研究を進めてきた。その中で、「態度」や「知識」を考慮しながら、関連性を持たせることの重要性も改めて認識してきた。そこで、今年度は、昨年度考えた3つを柱にして研究をより深化させることによって、学習内容が明確になると考え研究を進めてきた。
まず、『毎時間の授業において核(コア)となる学習内容を明確にすること』だが、昨年度の公開研究会では水泳を行い、「仰向けになって浮くこと」に関わる内容に焦点を当てて授業を行った。研究討議では、新学習指導要領の内容に関わって、1時間の授業の中でどの部分に絞って学習内容を明確にしたのかが主に議論された。仰向けで浮く場合「姿勢」が重要になるが、その中でも「腰がくの字に曲がらないように背中を伸ばして浮く」ことが挙げられた。これはこの授業での核となる学習内容であり、生徒に気付かせたい「かかわり」の重要ポイントだと強く感じることができた。授業の始めに浮きやすい姿勢について教師側から提示したが、単に要点を押さえた指導を行うのではなく、生徒に問いかけをする中で、まずは「生徒自らがこれまでの経験を生かした様々な体験をしてみる」ということが重要であることを強く感じた。今回初めて背泳ぎに触れる生徒も多いが、小学校で学習してきた内容(簡単な浮き沈みやクロール、平泳ぎなど)を参考にしたり利用したりすることで、既習内容との「かかわり」に気付かせることにつながると感じた。また、“楽に浮く”ことを考えさせることで、「腰を曲げずに背中を伸ばすこと」だけでなく、「全身の力を抜くこと」や「頭の向き(あごの位置)」など、他の様々な要素も重要であることに気付かせることができると感じた。明確な学習課題を提示すると共に、試行錯誤する時間を確保することも重要であるので、修正して授業づくりを行っていきたい。さらに、学習内容が多すぎたことも課題として挙げられたので、欲張りすぎず内容を絞り込んでいくことも考慮したい。このことは他の単元・種目でも活用ができるので、今後の研究に生かしていきたい。
次に、『伝える活動(≒言語活動)』については、昨年度まで行ってきた学習ノート(授業で学んだことや悩んだことなど)への記入だけではなく、「コツ」や「ポイント」を押さえた適切なアドバイスやコーチングによって、技術や情報の共有化することが大切であると考え実践してきた。単なる言葉かけではなく、教師側がしっかりとした視点を与えた上で課題を提示することが重要であり、それが本時の学習と既習の学習がつながり、かかわりを見いだせるキーワードにもなると感じた。今回の水泳の授業では、ほとんどの生徒が積極的にコミュニケーションをとりながら練習に熱心に取り組んでおり、中には1つ1つ丁寧にアドバイスする場面も見られた。しかし、中には学習内容が多く、アドバイスするこつやポイントを理解しきれない生徒もいたので、内容や視点を1つか2つに絞ることで、当を得たアドバイスやコーチングができると感じた。このことは他種目での指導にもいえることなので、今後改善していきたい。
最後に、『学びを見取る活動』については、全体研究とのかかわりで述べたように、各授業の後半でゲーム的な要素を積極的に取り入れ、単に技術の習得状況を見るのではなく、「学んだことを生かした動きができているか」「既習のものから選んだりしているか」などを評価することで、要点を理解した学習ができているかを確認することにもつなげることができた。また、作戦タイムや意見交換の場を意図的に設けることで、「ポイントとなる内容を理解した説明や発言をしているか」「説明が分かりやすいか」などが見取れるような授業づくりに努めた。その結果、コメントの内容だけでなく、徐々に質の高いゲームの様相が見られるようになってきたので、研究の成果をあげることができた。
今後の課題は、主に小中の連携である。今年度は年度当初から附属小学校の協力を得て行っていく計画であったが、学校行事や時間割の関係から、情報交換や授業観察にとどまってしまい、ゲストティーチャーなどの形で直接指導を行うことができなかった。今後も可能な限り実践できるような調整を行っていきたい。
参考文献
「中学校新学習指導要領保健体育科」文部科学省
「指導と評価-学校の学力と社会で生きる力-(高橋健夫)」平成14年日本図書文化協会
「健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会これまでの審議の状況」平成20年中央教育審議会議会


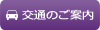



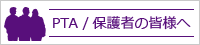

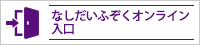

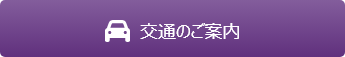
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp