美術科総論
美術科
研究主題「感性を豊かにし,生徒が主体的に取り組む題材の開発」
~学びの「つながり」を意識した活動を通して~
小田切 武
1.主題設定の理由
本校の美術科では、前回までの3か年の研究で「生徒が学びを実感できる題材の開発」をテーマとしてきた。「生徒が学びを実感する」とは、「生徒自身が本来持つ資質や能力の高まりを自覚する」ことである。子どもたちは発達の過程で、さまざまな経験から自分と周りの世界とを感覚や感情、動作によって確認し、自ら育んできた資質や能力と関連づけながら自己を更新し続けている。
ところで平成16年度に行われた国立教育政策研究所の調査によると、総じて子どもたちは、図工・美術に高い興味・関心を示してはいるが、役に立つか立たないかというアンケートではそれ程役に立たないかもしれないと回答している傾向がある。これは民間機関での調査でもほぼ同様な傾向が現れているようであり、経済状況によって最初に文化的事業の予算がカットされる大人社会の認識ともつながるものである。このようなことからも「学びを実感する」ことが、子ども自身その重要性を感じ、主体的に取り組む姿勢につながるのではないか、ひいては教科としての必要性を認識することにもつながるのではないかと考えた。
ところが、資質や能力がはっきりと目に見て現れるものは良いけれども、発想力が豊かになったとか、創造的に制作できるようになったなど、数値化できない抽象的なものを実感するためには、生徒自身が日頃から意識し、自分がどの位置に立っているかを常に自覚する必要がある。前回までの3か年研究の実践をしての反省では生徒一人ひとりが本当に学びを実感できていたのかをいろいろな角度から検証する必要があり、その時間が実際にはあまりつくれなかったことが今後の課題であり、今後とも授業ごとクラスごと個人ごとに生徒の様子を適切に読み取り、必要な支援を行えるようにしたいとまとめている。
そこでまず「学びを実感する」ためには、平成24年度から実施される新しい学習指導要領に「感性を働かせながら」とあるように、本来持っている自分の感覚や活動を通して「形や色、組み合わせなどの感じをとらえ」、「自分のイメージをも」つことを確認していく必要がある。その上で、社会的な現象や文化的な概念などもツールとして使える中学校での「感性を豊かにし」て、現在学んでいることが、今までの学びとどうつながっているのか、これからどうつながっていくのかを生徒自身が認識し、自ら主体的に取り組む題材を考えていかなければならないと感じている。このような目的で設定された題材に取り組む中で、生徒が自己の学習結果に対する期待や自信を持つことができれば、希望や可能性を進んで広げていこうとする姿勢にもつながっていくものと考える。題材に取り組む→自信→次の取り組みへの意欲→次の題材に取り組む→・・・と、このサイクルがスパイラル的に高まることで、生徒が学ぶ意欲を感じ取り、ひいては生きる自信を持つという自己肯定的意識が高まっていくものと考えている。そのために、生徒の主体的な学習活動、つまり互いに認め合い、自己表現や自己発揮ができる学習、粘り強く取り組める学習を今後も引き続き構想していきたいと考えている。この学習構想に基づき、学ぶ過程や学んだ成果に自信や達成感を感じることができる授業づくりを目指していきたい。
この主題を追究するためには、題材が生徒の実態に即しているか、学ぶべき内容がふさわしいかを確認することが必要であろう。そして授業の中にいかに生徒がかかわりを見出し、学びのつながりを意識し、主体的に取り組む活動を仕組んでいくか、また生徒自身が資質や能力の高まりを自覚できるような教師の働きかけや評価のあり方にどのようなものがあるか、このようなことを念頭に置きながら中学校の3年間を通して総合的に生徒の成長に寄与するための研究をしていきたいと考えている。本年度は上記研究テーマを掲げ3か年計画の3年目にあたる。過去2年間で進めてきた研究の成果と課題を確認し、まとめを行っていきたい。
2.全体研究との関わり
平成24年度から実施される学習指導要領では、習得、活用、探究の学力の過程が「生きる力」につながるとし、理念的なものは変わらないものの現行の指導要領からの改訂のポイントとして、基礎的・基本的な知識、技能の確実な定着とそれらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の育成などを掲げている。美術科としては表現や鑑賞の指導を通して、小学校から共通に働く資質や能力([共通事項])を育成することが新たに加わり整理されたが、これは全く新しいものではなく今まで大事にしてきたものをまとめたものである。この[共通事項]をしっかり押さえること、つまり形や色彩、材料などについて意識して取り組むことは、美術の授業だけでなく、普段の生活の中でも形や色彩を意識し豊かに感じ取れる子どもたちを育てられるようにしたい、さらにはビジュアルな文化社会を豊かに生きていけるようにしたいという考えの基に設定されたものである。これは本校で目指す研究テーマともリンクする部分である。
全体研究の中で、繰り返し使われている“かかわり”を本年度も踏襲し、引き続き「学習内容の関連性」について研究を進めていく予定である。美術科における“かかわり”とは、「これまで生徒が小学校の図画工作科をはじめ様々な学習や日常の生活の中から獲得してきた資質や能力を、美術の表現や鑑賞の幅広い活動から感性や感覚、想像力を働かせた体験を通してさらに高め、日常生活との相互のかかわりによって高めていくこと」とした。生徒の実態に合わせ、生徒が意欲的に取り組める題材を設定し、評価や学習活動を通して生徒が自分の資質や能力の高まりを実感し、その喜びを味わいながら活動を続けていけるように工夫していくことが大切である。美術科では、生徒自身が学習活動を通して自己の資質や能力の高まりを実感することができるよう、感じ取ったことをもとに主体的に取り組む題材や学習活動を仕組んでいきたい。
3.研究計画
1年次 生徒の実態に則し、生徒が主体的に取り組む題材開発について
- かかわりを見いだし、学びのつながりを意識した題材の開発と実践
- 題材・授業においての基礎・基本の明確化(1年生にとってどのような資質、能力を育てるか)
3年計画の1年次として、生徒の実態に則し、生徒が主体的に取り組む題材の開発について研究を進めた。新学習指導要領を視野に入れ、小学校からのつながりを考慮し、形や色彩からイメージをふくらませたり、美術作品を読むということを通して鑑賞の能力を高め、それを基に創造力を働かせる取り組みを題材として設定した。
形や色彩からイメージをふくらませる題材では、オートマティズムの技法によって制作された素材を基にコラージュで「表情のある顔」を制作した。意欲的にそれぞれの技法を試し、比較的のびのびと制作に取り組んでいる様子がうかがえた。この点から中1ギャップを概ね回避できたのではと思っている。しかし、新たに自ら技法を見つけたりあみ出したりというところまでにはもう少し時間が必要だと感じた。また、オートマティズムによってできた素材にタイトルをつけるという課題を与えることにより、偶然できた形や色彩からインスピレーションをわかせ、イメージをふくらませるように努めた。詩的なものやこちらが思わずはっとするようなタイトルをつける生徒もいた。反面、コラージュ技法で表情をつくっていく過程においては受け止め方が固く、難しく捉えてしまった生徒もいて、現実の顔から逸脱できず(輪郭や髪型、目やクチなどの位置)にいる生徒もいた。このような生徒は、他者の目が気になり、なかなか思ったことを言葉にできないでいることも理由の一つとして考えられた。そのため、この次の題材では、型にはまらず、自分の感じたこと考えたことに自信が持てるよう声かけを行い、表現させたいと考えた。
上記のような思いから、美術作品を読むことを通して鑑賞の能力を高め、それを基に創造力を働かせる取り組みを題材として設定した。教科書や資料集、画集などから自分が気に入った作品を鑑賞し、その作品をもっと素敵に、もっと面白く変化させる「チャレンジ!アレンジ・アート」では、絵画作品の読み方を学び鑑賞の能力を高めることができた。それは、作品をアレンジするためには元の作品がどんなメッセージをもっているか、また作品をみる人にどのような印象やイメージを与えているか、描かれた作品の時代背景にはどんなことがあったのかなど、自らの感覚や知識などをもとに考えなければならないからである。生徒は既習の学習や日常の中で社会とのかかわりを見いだし、題材に取り組んでいる様子が伺えた。単純に作品から受けるイメージを別のものに置き換えて面白い作品を制作した生徒もいれば、地球温暖化や経済不況による社会問題を取り上げた生徒もいた。ただ、知的好奇心旺盛な生徒たちなので、社会事象を絡めた方が良いだろうということからオリジナルの作品を半ば無視して強引にアレンジをしている生徒もおり、こういった生徒には、もう一度自分が選んだ作品についての根拠を明確にし、取り組むように示唆した。
フィードバックし考え直すきっかけを与えることにより全体としても作品鑑賞の基礎が築けたものと思っている。しかし、発想することや創造的に工夫し表現することについては、今年度ステップアップできたことを基にこれからも引き続き研究を進めていきたいと考えた。生徒がかかわりを見いだし、学びのつながりを意識できるような題材を考え、ワークシートなどの内容についても考えていく必要性を実感した。
2年次 生徒がかかわりを見いだし、学びのつながりを意識した指導と評価の在り方について探る
- かかわりを見いだし、学びのつながりを意識した題材の開発と実践
- 生徒が学びのつながりを意識し主体的に取り組むことができるワークシートの工夫について
2年次では、鑑賞で培った視点を、更に現代の社会へと視野を広げ、グループ活動を通して感じ方、考え方を形や色彩、材料などを基にイメージを持たせ、発想・構想し創意工夫して更なるレベルアップを図っていきたいと考え「わたしたちがつくるかんきょう(環境、感興、感・供)アート~グループワークでかんきょうを考える」という題材に取り組んだ。「生徒が学びを実感する」ことが次への活動に主体的に取り組むことにつながるための重要な要素と考えているため、題材に取り組む前後でどういう位置に自分がいるのか確認する必要を感じた。学びを実感するとは、「生徒自身が本来持つ資質や能力の高まりを自覚する」ことである。資質、能力の高まりを実感することは目に見えるものは分かりやすいがそうでないものを実感するということは、ある一定の期間の中で自己省察する場面を設定する必要があった。そこで、アンケートを上記題材の事前事後で実施した。まず、美術に対する関心・意欲・態度についてであるが、関心としては決して高いわけではなかったが、概ね真面目に取り組む姿勢は持っていた。小学校時と比べるとよくやっていると回答した生徒が半数近くいることにも、(あくまで比較であるが)前向きに取り組む姿勢につながっているものと感じた。努力を要すると回答した生徒には大きく分けて2種類おり、自分のイメージしたことを表現として上手に表せないもどかしさからのものと忘れ物が多く提出が守れないというものであった。2年次の活動から、更に美術に対して意欲的に取り組んでいると答えた生徒が相対的に増えたことは成果としてあげられる。 次に発想・構想の能力については、今までの取り組みを見てみると教科担当としては、まだまだ堅さがあるように感じるわけであるが、生徒たちは豊かになったと感じている生徒が6割強いた。発想が乏しくなったと答えた生徒には、明らかに知識は増えたのだが、そのことによっていろいろ考えてしまい思うようにアイデアが浮かばなくなったと答える生徒が多かった。知識を活用する能力が求められているとともに、よく分からないと答えた生徒も含め自己評価能力を高めていくことの必要性も明らかになった。そこで本題材では、自分の考えに自信をもつための方策として、またアイデアを思いつくきっかけとしてグループ学習で制作していくことにした。協力しながら、他者の意見を聞き、仲間の意見に感心しつつ、もっと良いアイデアを出そうとする姿勢にもつながり、明らかに「思いつかない」と答えた生徒の数が減少したことは評価できると思っている。
創造的な技能についても発想構想の能力と同じような結果がでているため上記のものとあわせてレベルアップができるよう今後も図っていきたい。
鑑賞の能力であるが、これは初年度の題材において、作品鑑賞をもとに自らの解釈を交えて名画をアレンジするという題材を行ったことが良かったのか、以前よりも劣ったと感じている生徒がいなかったのは成果としてあげられる。この題材を行う以前は、ただ何となく作品を見ていたものが、細かいところまで観察し、または作者の人生や時代背景にまで広げて鑑賞することで、以前では気づかなかったことや違う感じ方ができるようになったと答えた生徒が多かった。よく分からないと答えた生徒が3分の1ほどいるので、引き続き見る観点などを意識した言葉かけや働きを行っていきたいと思った。「わたしたちがつくるかんきょうアート」の題材では、一般的に言うファインアートとは違うので、絵画や彫刻を鑑賞することが目的と考えている生徒にとっては、この題材の中にそのような取り組みをしていないことで、よく分からなかったり以前よりもできないと答えた生徒もいたが、視点を増やし作者がどのような考えのもとで制作したかを推しはかったり、共感することの楽しさや日常生活の中にも色々なものに関心を向け考えることができるようになったと答えた生徒も出てきており、鑑賞の能力の高まりを感じることができた。
上記の美術科での観点を美術室にわかりやすく掲示するなど、今後も常に意識させ資質・能力の向上に努めていきたいと考えている。
3年次 生徒がかかわりを見いだし、学びのつながりを意識し主体的に取り組む題材の開発とその実践(本年度)
- かかわりを見いだし、学びのつながりを意識した題材の開発と実践
- 題材のねらいに則した生徒の活動の読みとりについて(評価のあり方)
- まとめ(成果と課題の検証)
4.本年度の研究
(1) 本年度の研究方針
○かかわりを見いだし、学びのつながりを意識した題材の開発と実践
○題材のねらいに則した生徒の活動の読みとりについて(評価のあり方)
○まとめ(成果と課題の検証)
(2) 研究内容
①生徒が、かかわりを見いだし、学びのつながりを意識し主体的に取り組む題材を引き続き開発し実践する。
- 過去の学習で学んだことや自分自身の生活体験から得たことなど、また総合的な学習の時間(本校ではSELF)や学校行事、他教科との学びをリンクするなど、生徒がそれらを新たに組み替えたり、学んだことを組み入れたりしようとするような題材を開発する。
- 生徒が自ら学びに生かせるワークシートや評価方法を工夫し、自己評価能力を高めるための手だてを講じる。
②学びのつながりからどのような資質・能力の育成に寄与するか、また生徒の様子を的確に把握できる教師の「読み取り」の工夫をする。
- 生徒の思考の過程や変化がわかるワークシートの構成や活用方法を工夫する。
本年度は上記のような視点を意識して「附中現代徒然草~形や色で、つれづれなるままに~」という題材に取り組みたいと考えている。これは『徒然草』のように、日頃感じていること考えていることをテーマに、自分たちが生活しているこの日本を意識しながら、思うままに形や色彩、適する材料を選び表現していって美術科が目ざすテーマに迫りたいと考えている。また本題材に取り組んだ後、昨年度実施したアンケートを再度行い、比較検証し、3か年の研究のまとめを行っていきたいと考えている。
《参考文献》
- 「中学校学習指導要領の展開 美術科編」 遠藤友麗 編著 明治図書 1999
- 「新しい学習指導要領を読む 図画工作・美術」 日本文教出版 2008
- 「美育文化5 2008 Vol.58 No.3 特集 新・学習指導要領を読む」


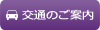



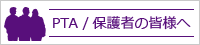

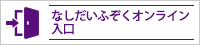

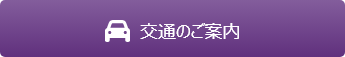
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp