平成22年度 理科総論
理科部会研究主題
生徒の素朴概念から立ち上げた授業の工夫
宮澤和孝・内藤波矢登・小崎由加里
1.主題設定の理由
(1)なぜ生徒の素朴概念をもとにした授業なのか
近年理科教育の中で生徒の自然に対する概念について研究が盛んに行われてきている。この、概念という言葉であるが、どこに焦点を当てて研究するかによっても、その呼び名は様々あり、統一された用語はないようである。(例えば、素朴概念、子どもの科学、ミスコンセプション、プリコンセプションなど。)本校では、生徒が、これまでの生活体験や、学習の結果持っている科学的に精緻化されていない自然の事象に対する知識や考え、概念などを表す言葉として「素朴概念」という言葉を用いることにした。生徒のこれまでの生活体験や、学習の結果持っている「素朴概念」を、中学校での学習を通して、「科学的概念」に変容・再構成していくことを本校では目指している。ただ、この「科学的概念」は、真に現在の科学で正しいとされている「科学概念」とは少し違う部分もある。例えば、中学校では、原子はそれ以上分けることができない粒子と定義するが、実際は、陽子、中性子、電子やその他の素粒子に分かれることはあり得ることである。しかし、生徒の粒子概念を育てる第一歩として、中学校の段階では原子が最小のものであると教える方が、生徒の中に様々な混乱を生むことなく粒子概念を導入できると考える。そのため、「科学概念」とは違ったものであるが、生徒が、「科学概念」の獲得に向かう第一歩として「科学的概念」の形成を行っていこうというのが本校の考えである。
この、生徒の「素朴概念」に関する様々な先行研究の結果、明らかになってきたこととして、素朴概念をより科学的なものに変容させたり再構成したりすることは非常に困難であるということがあげられる。にもかかわらず、その研究の成果が、実際の教育現場ではなかなか生かされてはいないのが現状であろう。素朴概念に関する調査の中で、慣性に関する調査結果を目にする機会に恵まれ、愕然としたことがあった。それは、ある調査問題について小学校6年生から高校2年生くらいまでその問題の正答率がほとんど変化していなかったからである。慣性については中学校3年生で学習する内容であり、その学習を終えた後では、その調査問題が答えられるはずの知識は習得しているのに正答率はその後もまったく変化していないのである。このとき、改めて、素朴概念をより科学的なものへ変容させることの難しさを思い知らされた。
今、我々理科教師に求められていることは、生徒に生きて働く知識を身につけさせることであろう。生きてはたらく知識とは、一定の条件のもと提示されたり、ある特定の言葉で表現されたときにだけ理解できたり使えたりするものではなく、その知識を身のまわりの様々な自然現象に応用できるようなものであると考える。特に、生徒が科学的に誤った考え(素朴概念)を持っている事柄については、一見獲得したかに思える知識も素朴概念が障害となってその知識を応用して考えることができないようである。
子どもの科学的概念あるいは、科学概念の形成における障害となっているものとして、生活体験による科学的に誤った概念(素朴概念)の形成、学習による新しい知識の不適切な結合、理解や思考の状況依存性などがあげられている。これは、学習によって獲得された一つ一つの事柄が、バラバラのままで生徒の中に位置づいていて、関係のあるもの同士のかかわりを意識できず、科学的に正しく構造化されないままに身に付いてしまっているということが原因の一つであると考える。こういった問題点が明らかになってきている以上、我々理科教師は、この問題を解決し、生徒の素朴概念をより科学的なものに変容させたり再構成したりする努力をするべきであろう。そして、その結果、生徒の素朴概念をより科学的なものへと再構成することが出来れば、そこで獲得された知識は、構造化された知識として、生徒の中にしっかりと定着していき、生きてはたらく知識となるであろう。
そこで、生きてはたらく知識を身につけさせるためには、生徒が元々持っている自然に対する知識や考え(素朴概念)をもとにした授業づくりを進める必要があると考える。これまでの生活経験などで持ち得た素朴概念に、学校で学習する科学的概念を結びつけ、そこで新たに作られるネットワークを科学的に正しいものへと組み替えていくことが大切なのである。だからこそ、素朴概念がどういう状態であるのかをつかみ、獲得させたい科学的概念をどこで、どのような手段でつかませていくのかを考え、単元の指導計画や、授業の流れの構造化を図ることが必要なのである。このような、工夫や努力を粘り強く続けていくことにより、生きてはたらく知識を身につけさせることができるであろう。また、この課程で獲得していく思考力・判断力・表現力や問題解決能力などは生きてはたらく知識と結びつき、生徒にとってこれからの社会をよりよく生きるために、はたらく力となるであろう。以上のような理由から研究主題を設定した。
(2)全体研究との関わり
全体研究における研究テーマは「知の再構成を目指して」~「かかわり」を生かした学習過程の工夫~であり、研究内容は
1)「かかわり」を見いだす課題・活動の設定
2)学んだことを伝える活動
3)学びを見取る評価
の3点を重点項目としてあげている。このうち2)の学んだことを伝える活動は、理科部会の研究テーマにせまるために必要不可欠であると考える。例えば、予想における討論、分析・解釈に関わる討論、または、予想や分析・解釈について、レポートに自分の考えを記入する活動を行うことにより、生徒の伝える力は高まっていくと考える。その結果、この力は、生徒の素朴概念をより科学的なものに変容させたり再構成したりするために有効に働くであろう。ただ、このことを特に取り上げて研究を行うことは理科の研究の本則ではないと考える。そこで、理科部会では全体研究の、重点項目のうち1)「かかわり」を見いだす課題・活動の設定と、3)学びを見取る評価について取り上げ研究を進めていくことにした。
① 「かかわり」を見いだす課題・活動の設定について
理科教育で目指すべきことは、生徒に必要な知識ばかりを教えこむことではなく、自然界の様々な事象同士の関連を見出させることであると考える。これは、一見何の関わりもないような事象同士の中に、同一性を見出し、自然界の中に存在する規則性や法則性を発見する活動である。また、この活動を通して見出した同一性を様々な事象に当てはめたときに見られる多様性に気づかせていくことも重要である。このような活動を日々の授業で繰り返し行うことにより自分が持っている知識を総合して課題を解決するような力を身につけさせることが出来るであろう。つまり、身のまわりの様々な場面に応用できるような、生きてはたらく力を身につけさせることができるのである。いくら知識を教えこんでも、それら一つ一つのつながりや、身のまわりの事象とのかかわりを意識させることなく、全く別の関係ないものとして、生徒の中に位置づいてしまえば、「これはこれ。それはそれ。」というように、深くかかわりのあること同士を無関係のものとして判断してしまい、結局、身のまわりの事象に当てはめたときに重要な同一性に気づくことは出来ない状態になってしまう。これでは素朴概念をより科学的なものに変容させたり再構成したとはいえない。一つ一つの事象がお互いにどのようなかかわりやつながりがあるのか、どのような同一性や多様性があるのかを生徒自身に見出させ、明らかにしながら、その一つ一つの細かなネットワークを科学的に正しく築きあげるようにして身につけさせることが大切なのである。このような考えで、生徒に様々な事象間の「[かかわり]を見出させる」ことにより、学習事項同士や学習事項と身のまわりの事象の関連性が生徒の中で構造化され、知の再構成が進み、素朴概念を科学的概念へと変容させることができると考えた。
②学びを見取る評価について
理科部会では、素朴概念をより科学的なものに変容させたり再構成したりする学習活動の中で、自己評価活動の占めるものは非常に大きいと考えている。自分がもともと持っていた考えと学習の結果得た考えがどう違ったのか、なぜ変わったのかを分析させ、その変化を見てどう感じるかを書かせるような自己評価活動を行うことによって、理科学習の有用性を感じさせ、新たな学習への意欲を高めることができるであろう。また、この活動が、自分の誤った概念(素朴概念)に気づき、科学的に正しいものへと軌道修正する力を育てることにもつながると考える。このような自己評価活動は、素朴概念をより科学的なものに再構成する活動を側面から支える重要な活動であるといえる。
また、このような自己評価の記述から教師が生徒の質的な変容を見取ることができると考えた。自己評価を用いて生徒の変容をつかみ、必要に応じて、アドバイスを与え、授業の内容にフィードバックするような指導と評価の一体化を図る活動は、科学的概念を定着させる上で欠かすことが出来ないものであると考える。さらに、研究を行う以上、その効果がいかがであったのかを見取ることは必要不可欠である。この見取りを自己評価活動と合わせて行うことが出来るならば、我々の限りある時間を有効に使う手助けとなるであろう。そこで、上記の自己評価活動の方法を工夫しながら、ここにあげたいくつかのねらいを達成できるように実施しようと考えた。具体的には、学習前の考え、学習の履歴、学習後の考え、この学習を通して自分がどのように変容したかの見取りを記入する1枚ポートフォリオを用いて行うことにした。
(3)新しい指導要領から
平成20年3月、新学習指導要領が告示された。現行の学習指導要領の理念である「生きる力」をはぐくむという点は、新指導要領に引き継がれた。この理念を実現するための具体的な手段の確立を目指し、今回の改訂が行われた。新指導要領の総則にある「基礎的、基本的な知識および技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくむとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い・・・」という部分にその理念を実現させるための具体的な手段が表れていると考える。これにともない理科としての改訂のポイントは「自然の事物・現象に進んでかかわり・・・」、「科学的に探究する能力の基礎と態度を育てるとともに・・・」という目標の文章から感じられる。それは、自然の事象に対するより積極的な態度の育成、科学的に探求する能力の基礎の確実な定着、そして、これらを活用して課題を解決する力の育成であると考える。本校の研究も、この新指導要領の理念に従い、それを具現化するための実践でなければならないと考える。
前述の通り、本校理科部会の研究テーマは「生徒の素朴概念から立ち上げた授業の工夫」である。生徒の素朴概念を科学的概念へと変容させたり、再構成したりすることをねらいとしている。素朴概念をより科学的なものに変容させたり再構成したりすることができれば、そこで獲得された知識は、構造化された知識として生徒の中にしっかりと定着し、原理・原則の転移が期待できるとともに新たな概念獲得の手助けとなり、生きてはたらく知識となるであろう。そして、素朴概念をより科学的な概念へ再構成するための学習活動を通して、生徒の思考力・判断力・表現力や、問題解決能力の高まりも期待できると考える。
さらに、テーマにせまるために本校で取り組んでいる工夫の中でも、予想、実験、分析・解釈の流れの確立と、1枚ポートフォリオによる生徒の自己評価は新指導要領の理念を実現する具体的な手段として有効であると考える。1枚ポートフォリオを工夫して利用することにより、生徒は学習の成果を感じ、それが次への意欲となり、効果的な学習を支える大きな力となるであろう。さらに、1枚ポートフォリオを用いた自己評価を繰り返し行うことによって、自分自身を客観的に見つめる能力を育てることができると考える。自分自身を客観的に見つめ、場合によっては軌道修正することができるような力は自ら課題を解決するためには欠かせない力であると考える。
このような点から、本校理科部会の研究は、確かな学力の育成にもつながり、新しい学習指導要領の理念を具現化する手だてとしても有効であると考える。
2.研究仮説
生徒の素朴概念から立ち上げた授業を工夫して行うことにより、自然を調べる態度や能力が向上し、「より科学的に再構成された概念(科学的概念)」を持った生徒が育つであろう。
3.検証計画
研究授業を行う単元において事前、事後調査を用いた自己評価や実験レポートの記述を利用して変容を追いかける予定である。
4.研究内容
(1) 研究の経過
本校理科部会における過去2カ年の研究テーマ、研究内容は以下の通りである。
①平成20年度
a 研究主題 生徒の素朴概念から立ち上げた授業の工夫
b 研究内容
- 生徒の自然に対する概念をもとにした授業の実践
- 自己評価や、教師の見取りに用いるための1枚ポートフォリオの工夫
- 生徒の概念をより科学的なものに再構成するための年間指導計画の作成
②平成21年度
a 研究主題 生徒の素朴概念から立ち上げた授業の工夫
b 研究内容
- 生徒の自然に対する概念をもとにした授業の実践
- 自己評価や、教師の見取りに用いるための1枚ポートフォリオの工夫
- 生徒の素朴概念をより科学的なものに再構成するための年間指導計画の作成
(2) 研究内容
① 素朴概念の調査問題の工夫と実施
② 素朴概念をもとにした、単元の流れの工夫
③ 問題解決的な学習の効果の確認と推進
④ 予想、分析・解釈における討論の充実の効果の確認と推進
⑤ 生徒自身が学習の成果をつかむ活動の工夫(1枚ポートフォリオ、実験レポートを用いた実践)
⑥ 指導と評価の一体化
⑦ 素朴概念をより科学的なものに再構成するための年間指導計画の作成
⑧ 新指導要領に対応した指導のあり方の検討
5.本年度の研究
(1) 平成22年度の研究重点
「生徒の自然に対する素朴概念をもとにした授業の実践」
「自己評価や、教師の見取りに用いるための1枚ポートフォリオの工夫」
「素朴概念をより科学的なものに再構成するための年間指導計画の作成」
「新指導要領に対応した指導のあり方の検討」
(2) 平成22年度の研究内容
①生徒の自然に対する素朴概念をもとにした授業の実践
生徒の素朴概念から立ち上げた授業の工夫として次のような具体的な活動を行うことにした。
ア 生徒の素朴概念の調査問題の工夫
これまでの研究の中で、自然の事象に対して生徒があらかじめ持っている素朴概念を調査するためにどのような調査方法を用いたらよいかを工夫してきた。素朴概念を調査する方法としては、素朴概念調査法、コメット法、文章分析法、論文法、概念地図法、パフォーマンステスト法などがあげられる。これら一つ一つについて、違った特性があるため、その特性をつかむとともに、実際にこれらの方法の特性を考えながら、様々な単元に関する生徒の素朴概念を調査するにはどの方法を用い、どのような質問がよいのかを検討した。このような検討の結果、これまでの研究を通して次のような視点が必要であると考えた。
- 単元全体の学習内容について、網羅的に調査するのではなく、中心となる科学的概念に焦点を当てて調査する。
- 調査問題に対する答えを書かせる際、その理由も含めて、図で表すことができるような内容のものについては、図も併用して答えさせる。
- ある一つの問題形式にこだわらず、調査方法の特性を理解した上で、調査する素朴概念に合わせて多様な問題形式を工夫する。
- 記憶していれば答えられるような問題ではなく、素朴概念がより科学的なものに変容しなければ答えられないような問題を工夫する。
このような調査により、これから学習する事項に対して、生徒がどのような素朴概念を持っているか事前に調査し、その結果を生かして授業や、単元の流れを計画していくことが大切である。
イ 素朴概念の調査結果をもとにした単元の流れの工夫
| ① 本単元で学習する内容に関して、生徒の既有の素朴概念を調査する。 既有の知識の限界を感じ、科学的概念のイメージの形成をする 実験1 ・・・ ② 課題に対して自分なりの予想をたてる。(素朴概念の表出) ③ 予想をもとに討論を行う。 ④ 課題を解決する方法の検討を行う。 (生徒が行う場合と教師が行う場合がある) ⑤ 自らの課題を解決するための調査活動を行う。 ⑥ 調査結果からわかったことを分析・解釈する。 (結果からどのような結論が導き出せるのか、予想での考えをどのように変える必要があるのか、など) ・・・ 実験x ※ここは実験ではなく、実験1で学習した原理を適用できる身近に見られる現象をあげ、それに関して,クラス全体で検討し、討論するという方法で行う場合もある。 ⑦様々な事例の中から科学的概念に関わる同一性を見出す。 ⑧科学的概念に関わるイメージを科学的な用語に置き換える。 ⑨科学的概念を,身のまわりの事象と結びつけて考え、その多様性をつかむ。 ⑩新たな知識や考え方を振り返る自己評価をする。 図-1 科学的概念を獲得させるための学習の流れ |
上記のような事前調査により、生徒がこれまでの生活体験や学習などの結果持っている生徒なりの自然に対する論理をつかみ、それぞれの生徒が持っている素朴概念の対立点や、矛盾点などを明らかにすることによって学習の動機づけを行い、関心・意欲を高めるとともに、目的意識を持って授業に臨むようにしていくことが大切であると考える。また、事前調査の結果、多くの生徒が誤った考えを持っていることについて、様々な事例を通して調査活動を行ったり、生徒が持っている素朴概念を使ってその現象を説明させたりする中で科学的概念のイメージづくりや、自分の素朴概念を変更する必要性を感じさせることにより、科学的概念の導入や獲得をさせるように考えた。具体的には図-1の科学的概念を獲得させるための学習の流れを基本的な単元の流れとし、授業を行うようにした。
ウ 予想、分析・解釈における討論の充実、予想、実験、分析・解釈の流れの確立
基本的な授業のスタイルとして、予想、実験、分析・解釈といった②~⑥までの流れを日常の授業の中で常に行っていきたい。当たり前といえば当たり前のことであるが、予想の段階で、各自の素朴概念を表出させ、目的を持って実験し、実験を通して事実は何なのかを確認し、その結果から論理的に考え分析・解釈をし、学習の結果自分の考えがどのように変化したのか見つめさせていくことは、生徒の素朴概念から立ち上げる授業には必要不可欠なものであると考える。この流れの中で、充実した討論を行うことにより、様々な考えの存在に気づき、それらの考えと自分の考えの相違点や、共通点を見つめさせるような活動によって、素朴概念をより科学的なものに変容させたり再構成したりすることができると考える。前述の通り素朴概念は強固なものである。それを変容させるためには、このような活動を毎日の授業の中で行うことが大切なのである。さらに、この活動を通して、観察・実験の技能を高め、科学的に考える力を養い、自然に対する興味・関心を高めることもできるであろう。つまり、「確かな学力」をはぐくむこともできるのである。このような意味からもこの活動を日常の授業の中でしっかり定着させる必要があると考える。
②生徒自身が学習の成果をつかむ活動(1枚ポートフォリオの工夫)
学習の前後に生徒の素朴概念を調査し、その結果を比較することにより素朴概念がどのように変容したのかをつかむことができる。このような活動を通して授業の成果がどうであったかを教師がつかむことは、その指導法の改善のためにも必要なことである。さらに、授業を通しての変容を生徒自身がつかむ活動も指導法の改善以上に重要なはたらきをする活動であると考える。このような活動を通して、生徒は学習の成果を感じることができるようになるからである。学習の成果が感じられれば、それは次への意欲となり、効果的な学習を支える大きな力となるであろう。さらに、このような活動の繰り返しによって、自分自身を客観的に見つめる能力を育てることができると考える。自分自身を客観的に見つめ、場合によっては軌道修正することができるような力は、まさに生徒にとって生きてはたらく力であるといえよう。具体的には図-1の⑨の自己評価の場面で、学習前に自分が持っていた考えが学習後どのように変わったのかを1枚ポートフォリオを用いて書かせることによって行っていきたい。また、日々の授業で用いる実験レポートにも同様の自己評価を行う欄を設け、繰り返し自己評価を行わせることにより自分自身を客観的に見つめる能力を育てていきたい。1枚ポートフォリオについてはその構成を工夫し、1枚の紙の中で、自分の学習前の考えや、学習の履歴、学習後の考えを振り返りながら自己評価させていくようにしたい。学習後の自分の変容を見取らせて行くには、この1枚ポートフォリオは、大変有効であると考える。また、1枚の紙の中で、生徒の考えの変化や、学習の履歴の振り返りができるように計画することにより、教師にとっても生徒の変容がつかみ易くなるだけでなく、指導目標の明確化が図れ、指導計画の構造化もねらうことができると考える。
これまでの実践を通して、学習の履歴をまとめさせる部分では、学習した内容についてひと目で、わかるようなタイトルを自分自身で考え記入させること、毎時間ではなく一つの実験ごとや一つの節が終わったところでこれまでの学習の中でポイントだと思うことを自分で判断させて書かせること、これまでの学習内容と、今回の学習内容の関わりを考えさせ、書かせるなどの工夫を行ってきた。今後も様々な単元での実践を進めるとともに、引き続き、実験レポートとの併用の工夫も考えていきたい。
③素朴概念をより科学的なものに再構成するための年間指導計画の見直し
素朴概念をより科学的なものに変容させるためには、何をどのような順序で教えていくかということも重要な要素となる。これは、一つの単元で、何を、どのような順序で教えるかだけでなく、中学校で扱うすべての単元で何を教え、それら単元をどのような順序で行うかも検討する必要があるということである。例えば、これまで本校で行ってきた実践に、粒子概念に関わるものがある。この実践を通して、1年生の、身のまわりの物質の単元の、状態変化、水溶液、密度などの学習で粒子概念を導入することはこれらの学習内容を定着させるためには効果的であると考えた。さらに、2年生で、最初に化学変化と原子・分子の単元を行い、原子・分子の概念の導入と粒子概念の定着を図り、その後に、動物の消化や、電流の学習をすることによって、その学習内容の深い理解や、粒子概念のより確かな定着が図れるのではないかと考える。このように、関わりの深い単元をどのような順序で行い、各単元でどこまで教えるのかということを検討することは素朴概念をより科学的なものに変容させたり再構成したりするためには必要不可欠なものなのである。今後も上記のような各単元の関連を見直し、指導計画の工夫をするとともに、その指導計画をもとにした実践を行いよりよい年間指導計画の作成を行っていきたい。
6.昨年度までの成果と課題
(1)素朴概念の調査と、単元の流れの工夫について
素朴概念を調査し、その後の授業の流れに生かす研究の大きな成果は、これから学習する内容に関する素朴概念を事前につかみ、単元の学習の流れにそれを生かせるということである。このような事前調査を行うことにより、今まで漠然とは感じていた生徒の自然に関する素朴概念や子どもなりの論理を具体的な形でつかむことができ、それによってこの単元の中心となる科学的概念をどのような方法で身につけさせるか検討した上で授業に臨むことができるようになった。そして、この事前調査を利用して事後調査を行うことにより、生徒の学習の成果をつかむことができ、教師自身の授業の評価とすることができた。また、事前調査自体が、知的好奇心を喚起し、学習に対する関心・意欲を高めることが実感できた。また、学習の流れについては、生徒にとって難しい科学的概念ほどボトムアップ的な授業の流れが効果的であり、生徒の「なぜ。」、「どうして。」といった疑問を解決し、生徒自身が納得できるような単元の流れを工夫することが重要であると感じた。さらに、様々な素朴概念の状態の生徒がいる中で、単一な指導方法に囚われず、アナロジーを用いたり、体感させたりと多様なアプローチを行うことが、より多くの生徒の素朴概念を科学的に変容させるために必要であるといえよう。
(2)予想、実験、分析・解釈の流れの確立
予想の段階でしっかり考え、討論することは、自分の考えを明確にしたり、実験の視点が明らかになったり、調べてみたいという意欲を高めることにつながった。そして、観察・実験を通して実際に体験し、その結果から予想に対する分析・解釈をしていくことにより、これまでの知識と、観察・実験の結果を総合して科学的概念をつかんでいくのである。このように学習を進めることにより、誤った考えを訂正したり、漠然としていた考えを明確にしたりしながら、思考を練り上げていくことができると考える。しかし、こういった授業を行うためには、教師にも熟練した指導力が要求される。生徒の思考力、判断力や表現力を高め、素朴概念を科学的概念に変容させるために、このような流れで日常の授業を行い続けることも大切な視点だが、その活動を通して教師自身の熟練した指導力を培い、各単元ごと、学習事項ごとの指導のポイントを教師自身が気づき、工夫していくという視点も忘れてはならない。
(3) 生徒自身が学習の成果をつかむ活動
これまでは、生徒自身が学習の成果をつかむために実験レポートなどを使い、自分の学習前の考えと学習後の考えを比較させて変容を見取らせるようにしていた。しかし、学習の前後の考えを比較するだけでなく、その間の学習履歴も振り返らせることにより、どのような過程を通して自分の学習が進み、何がきっかけで自分の考えが変化していったのかを見取らせることは有効である感じることができた。ここ数年、このような学習履歴もあわせて見取るための1枚ポートフォリオを作成し、実践することができた。その中で、この1枚ポートフォリオを用いた実践は、生徒の変容をつかむ資料としても有効であるという事がわかった。今後は、これをいかに日常的な活動として取り組めるようになるかが大きな課題である。
また、このようにして作成した1枚ポートフォリオは教師自身の授業の評価にも大変有効であるといえる。授業の結果、生徒の考えがどのように変容したのかを見取ることにより、課題が明らかになるとともに、その解決策を検討し授業を改善するために大いに役立つ資料となることも確かめることが出来た。
これらの取り組みは、ただ単に自然に対する知識ばかりを詰め込むのではなく、生徒にとって「生きてはたらく力」を身につけさせるために重要な取り組みであると考える。しかし、素朴概念は強固なものであることも改めて痛感した。一つ一つの実践を通して、得られた成果を次に生かすとともに、一つ一つの課題を解決するような工夫を地道に行いながら、実践を続けることの必要性を感じた。
7.参考文献
(1) 堀哲夫著「理科教育学とは何か」東洋館出版社
(2) 堀哲夫編著「問題解決能力を育てる理科授業のストラテジー」明治図書
(3) 堀哲夫著「学びの意味を育てる理科の教育評価」東洋館出版社
(4) 松森靖夫著「子供の本音を知ろう!新しい評価法はこれだ」学校図書
(5) 日本理科教育学会編「これからの理科教育」東洋館出版社
(6) 日本理科教育学会編「理科教育学講座 第2巻」東洋館出版社


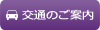



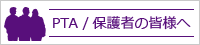

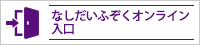

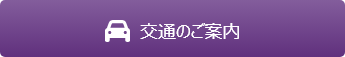
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp