数学科教科総論(平成22年度)
数学科研究課題
作業を重視した数学の授業の創造 11年次
萩原喜成 島口浩二 櫻井順矢
1.テーマ設定の理由
本校に入学してくる生徒は、計算力に優れ、知的好奇心も旺盛である生徒が多い。その反面、試行錯誤することよりも、How toに目を向ける傾向も強い。本校数学科が目指す生徒とは、1つのことにこだわり、じっくりと腰を据えて粘り強く考える力を持つ生徒である。たとえ素晴らしい解決に至らなくても、課題に対してあきらめずに、前向きに挑戦する生徒を育てたいと考える。しかし、「考える力をつけさせる」ことは簡単ではないし、考えるということを教えることも難しいことである。そこで具体的方策として、作業を重視した授業づくりの推進を考えた。
作業とは、古くは労作という言葉からきている。農作業等のように、実際に身体をつかってもの(食物等)を作り、汗をかいて働くことにより人格形成がなされ、直観が養われ、人の認識に大きく影響を及ぼすという教育学からきている。数学科で重視する作業とは、生徒自身が問題解決のために様々な関係を整理し、具体化させ、新しい場面でその関係を使っていくという活動である。作業を重視することによって、もてる力を総動員して課題に取り組み、考えさせることができる。また、手を使ってものをつくり、それを様々な角度から観察することによって思考が促進され、解決に向けての豊かな発想が生まれてくる。このような生徒の姿が本校数学科で目指す生徒の姿である。
具体的には、作業を重視することによって、次のような3つの利点があると考える。
| (1)ものをつくったり、手にとって観察したりすることで、生徒の思考が促される。また、別々に身に付けていた知識や性質どうしの関係、既有の知識と新たな課題との関係を捉えるときの重要なてがかりを得ることにつながる。そのことで、さらに思考が促されることになる。 (2)生徒は既有の知識や知恵を総動員して考える場面を得ることで、その解決を通して、考える楽しさや解決できたときのよろこびを味わうことができる。それが、課題に対してあきらめず、粘り強く取り組む姿勢を育てることにつながる。 (3)数学という教科の特性上、抽象的な思考の場面が多くかつ生徒の思考の様相は多種多様で、ひとりひとりの考えを教師がしっかり把握するのは困難なことである。しかし、作業を重視することで生徒の考えは、活動の中やノート上などに現れやすくなる。教師はその考えを把握しやすくなるのである。把握したものを生徒個人にフィードバックすることで、生徒に自分の思考過程を意識化させることができる。そのことは、個々に応じた指導にもつながる。 |
2.本研究の目的
本研究の目的は、作業を重視した授業を行うことによって、生徒に「考える力をつけさせる」ことにある。作業を通し、考え抜くことのよさや喜びを感じとることで、次の課題にもまた挑戦したくなるような生徒になると考えているからである。前述のような作業を取り入れることの利点をふまえ、五感を総動員させることによって、なお一層考えることに重きをおいた指導ができると考えたのである。本研究の目的を達成するためには、「作業を重視した数学の授業」についての研究を継続し、そのような授業実践を蓄積していくことが重要である。日々の授業の中で、生徒がじっくり取り組むことのできる教材を用意し、落ち着いて考える場を継続的に設定していく工夫をする。そうすることで、生徒は課題にじっくり取り組むことに慣れてくる。作業を重視した授業を継続することが、「考える力をつけさせる」ことにつながるのである。
10年間の研究の成果として、蓄積してきた授業実践の充実があげられる。これまでに31本の授業実践を行ってきているが、これらの実践と本年度の研究をふまえ、3年間の中でどのように授業を仕組み、生徒に「考える力をつけさせていくのか」ということも考えなければならない。一度実践した授業についても何年か継続して実践することで、さらに教材研究を積み上げることができ、授業を洗練することができると考えている。今年度も本テーマのもと他校の先生方に紹介できるような事例をさらに蓄積し、研究を重ねていきたい。


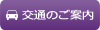



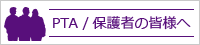

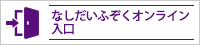

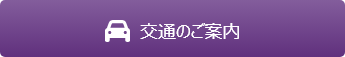
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp