数学科総論(平成28年度)
-数学科研究主題
考えさせる授業の創造
~ 振り返る活動を重視して ~
井上透 佐藤 治彰 日向 昭子
1.目指す生徒像と研究主題設定の理由
本校数学科で目指す生徒像は、1つのことにこだわりをもち、粘り強く考えることのできる生徒である。たとえ素晴らしい解決に至らなくても、問題の解決に向けてあきらめずに、誠実に取り組もうとする生徒を育てたい。そのためには、生徒が主体的に問題に向き合い、何とか解決しようと粘り強く取り組むような授業を数多く行うことが大切である。
授業での考える主体は生徒である。生徒が問題を解決したいと思うことによって、生徒は主体的に考えるのである。では、生徒に問題を解決したいと思わせるためにはどのようにすればよいのだろうか。教師が考えることを生徒に指示したところで、主体的に考えさせることはできない。教師が、授業において生徒を考える場におくことが必要であると考える。そのためには、教師の教材研究が最も重要である。教師が、内容の豊かな教材を用意し、生徒への提示の仕方を工夫し、生徒が考えている様相を見極め、それを生かすための工夫を凝らすのである。そこで、本校数学科では、「考えさせる授業の創造」を研究主題として設定し、教師の教材研究とその実践を中心的な研究内容として研究を進めていく。
「考えさせる授業」を目指した教材研究とその実践は、これまで本校数学科が最も重視してきた研究内容でもある。そこで、研究主題「考えさせる授業の創造」については、今後も普遍のものとしたい。副主題には、そのときの教育情勢や全体研究に合わせ、「考えさせる授業の創造」のための具体的な手だてとなるようなものを設定していくものとする。
2.本校数学科における「考えさせる授業」について
数学科でいう「考えさせる授業」とはどのような授業であるべきかについて、概観してみたい。もっとも重視しているのは、その授業で扱う題材である。どのような題材を用いて問題場面を設定するかによって、その授業の展開が大きく変わるからである。さらに、その題材を用いて、生徒に考えさせるための授業における工夫も重要である。ここではまず、授業で扱う題材について述べ、次に授業の流れを導入・展開・まとめという3つの過程として捉え、それぞれの過程において考えさせる授業を創造するための工夫について述べる。
□授業で扱う題材について
「考えさせる授業」においては「問題解決型」の授業が望ましいと考える。生徒にとって解決の必然性を感じられるような問題場面を設定し、生徒の「解決したい」という思いをもたせる題材を開発していきたい。そのような問題場面として、生徒にとって切実な現実世界の問題が考えられる。現実問題を数学化し、数学を使って問題解決するような授業である。ただ、中学校数学で解決できる現実問題はそれほど多いものではない。ときには、教えたい数学的な構造を現実的な場面で置きかえた「擬似モデル」(島田茂1977)のような問題や、数学の世界だけで考えられる数学的な問題を解決するような授業も考えられる。このような場合は生徒が考えずにはいられないような、知的好奇心をくすぐる問題場面の設定が求められる。
そもそも人はどのようなときに考え始めるのだろうか。杉山吉茂氏は、「人は、知識のズレや矛盾に気がついたときには、そのままでは放っておけないという心理的傾向を持っている」ことを指摘し、「考えるとは、矛盾のない首尾一貫した法則性の支配する世界を心内に作りあげることへの努力をすることだといってよいであろう。」と述べている。つまり、生徒を知識のズレや矛盾に気づかせるような状況におくことができれば、その生徒はそれを解消しようと考え始めるというのである。そのような問題場面に生徒を立たせることで、「その原因を探りたい」「その矛盾を何とか解消したい」という強い思いをもたせるのである。このとき、配慮しなければならないことは、単にその問題だけを解決することにねらいがあるわけではないということである。その問題の背後に潜む数学的な構造をつかむことに真のねらいがある。数学的な構造をつかむことができれば、数値が変わったり、問題場面が変わったりしても、数学を使って問題を解決することができるからである。このように考えてみると、数学的な構造をつかむために、それらの間にある関係を捉えたり、仕組みを調べたりするというねらいに主眼がおかれた問題場面の設定も考えられる。例えば、平方根の学習において、「√2が加わった新しい数の世界はどのような構造をもっているだろうか」という問題である。このような学習において、生徒が夢中になって考えている様子が見られることは、数学という教科のもつ特性であり、よさでもあろう。
「考えさせる授業」をするために、教師は、授業で扱う題材の数学的な背景まで含めた全体構造について研究しておく必要がある。その上で、生徒の考え方の傾向や生徒のもつ常識などを踏まえて予想される生徒の反応について丁寧に分析しておかなければならない。すなわち、教材研究こそが「考えさせる授業」をつくる上で最も重要だといえる。このような入念な教材研究の上に立って、初めて授業の中で生徒に考えさせることができるのである。
□授業の展開について
導入の過程においては、生徒がその問題を何とかして解決したくなるように、生徒がその問題場面に引き込まれるような工夫が必要となる。具体的には、生徒に与える情報について、映像や写真で与えるのか、数値データで与えるのか、実際に図をかいたり、模型を作らせたりするのかなど、さまざまな要素が関係してくる。さらに、その数値についても後の活動を想定して、吟味を重ねて設定する必要もあろう。いずれにしても、授業の導入の過程がうまくいけば、生徒はその活動にのめり込み、教師が指示をしなくとも考え始めるであろう。
展開の過程においては、生徒が問題に取り組み、試行錯誤をしている場面が想定される。生徒が夢中になって問題に取り組んでいるときには、十分な時間を確保して生徒の思考に委ねることが大切である。生徒が誤った方向に向かっていたり、行き詰まっていたりしている様子がみられても安易にヒントを与えて誘導するようなことはせず、じっくりと粘り強く考えさせるのである。生徒の誤りや行き詰まりは必ずしも悪いものばかりではなく、それを客観的に見直すことによって正しい考えや向かうべき解決へと思考が進むこともある。本校数学科でこれまで研究してきた「作業」は、自分の思考を客観的に見直す上で有効であった。例えば、正四面体と正八面体の面を合わせると全体として何面体ができるかという問題では、頭の中で考えてみると、互いに重なり合う面を考慮して4+8-2=10より、十面体になると予想する生徒が多い。しかし、実際に模型をつくらせてみると、2つの面で1つの平面をなす部分が3カ所あり、4+8-2-3=7より、七面体になることに気づく。生徒は自分の予想と異なるわけを知ろうと、その模型を注意深く観察し、必然的に二面角について考察を始める。このように、「作業」を重視することは、自分の思考を客観視する上で重要な役割を果たすのである。
また、教師が生徒の「作業」の様子をつぶさに観察し、他の生徒にとってよい刺激となる生徒の考えを全体で取り上げて、共有させることも有効である。それによって、生徒は教材について別の視点から見たり、自分の考えを改めて見直したりすることができる。教師は、どのようなタイミングで生徒に自分の思考を客観視させるかを見極めることが大切である。これもまた教師の教材研究の深さに依存する。また、どのような方法で生徒に自分の思考を客観視させるかも重要であり、上記はその一例に過ぎない。生徒がメタ認知できるような工夫をしたり、グループやペアを活用して、他の生徒との相互作用を促すような工夫をしたりなど、さまざまな方法が考えられる。
まとめの過程においては、生徒一人ひとりの考えや小グループごとの考えなどを全体で共有したり、共通点や相違点を見いだしたりして、学習内容を統合的にとらえてまとめたり、そこからさらに発展的にとらえて別の課題につなげたりなど、いわゆる練り上げの過程を大切にしたい。
3.全体研究との関わりについて
全体研究では、生徒が到達した「自分なりの結論」に満足している状況を打開して、それを吟味し、改善や発展を図るような授業を「深く考える」授業としている。本校数学科の目指す「考えさせる授業」も、目指す生徒像として「1つのことにこだわりをもち、粘り強く考えることのできる生徒」を掲げていることからも、同じ方向性であると考える。全体研究では生徒が「自分なりの結論」に満足している状態を打開するための手立てとして「視点を変える活動」を取り入れることとしている。
数学科では、「自分なりの結論」を、生徒が授業において考えた末に得られる知識や技能としての意味と、それを得るためにどのような過程を経たのかという、数学的な見方や考え方としての意味の2つの側面で捉えることとする。前者をプロダクトとしての「自分なりの結論」、後者をプロセスとしての「自分なりの結論」と呼ぶこととする。また、「視点を変える活動」については、プロダクトとプロセスのどちらの側面についても、「自分なりの結論」を再評価し、確証を得たり、改善や発展を図ったりすることにつながるものと捉え、それらを「振り返る活動」として「考えさせる授業」の実現のための手立てとしていく。
数学の授業において、「振り返る活動」というとき、どのようなものが考えられるであろうか。第1に、「作業」を通して振り返る場面が考えられる。本校数学科では、「作業」を重視した授業について研究を進めてきた。実際に手を動かすことで、内在する数学的な事実や自分の思考の様相が顕在化するため、生徒は絶えず、それらについて振り返りながら試行錯誤をすることになる。その結果、生徒は夢中になって問題に取り組み、粘り強く考えることにつながったり、顕在化した生徒の思考の様相を観察して評価に生かすことにつながったり等の利点がある。「作業」を通して顕在化される、事象に内在する数学的な事実は、「作業」によって得られた知識や技能であり、プロダクトとしての「自分なりの結論」ということができる。同様に顕在化される、自分の思考の様相には、生徒が用いた数学的な見方や考え方が含まれており、プロセスとしての「自分なりの結論」ということができる。(本校数学科でいう「作業」は、模型をつくったり、図をかいたり、計算を繰り返したり、念頭操作をしたりなど、広い意味で捉えている。)
第2に、授業ノートへの記述を通して振り返る場面が考えられる。「問題解決型」の授業において、問題を解決するにあたって見通しをもち、結論の予想や解決方法の構想を立てることは大切である。それらを授業ノートへ記述させることによって、ノート記述から自分の予想や構想について振り返る場面が考えられる。また、問題解決の過程を経て到達した結論の妥当性を検証することも大切である。ここでも授業ノートへの記述を通して、到達した結論やそこに至るまでの過程について振り返る場面が考えられる。その際、自分が暗黙裏に前提としていることに目を向けさせ、評価・改善をしていくことが大切である。見通しをもつ段階で立てる結論の予想や、問題解決の過程を経て到達した結論は、プロダクトとしての「自分なりの結論」ということができる。一方、解決方法の構想を立てたり、問題を解決したりする過程は、生徒が用いた数学的な見方や考え方が含まれており、プロセスとしての「自分なりの結論」ということができる。
第3に、問題を解決する過程において、他者との相互作用を通して振り返る場面が考えられる。自力解決において、ペアやグループを活用して他の生徒と交流しながら問題について考える際に、自分で見いだしたことがらやそこに至るまでの過程について振り返る場面が考えられる。また、全体で考えを発表し合い、共有するときに、発表された考えの共通点や相違点を挙げるなど比較検討をしながら振り返る場面が考えられる。他者と考えの交流をする場面では、見いだしたことがらについて振り返ることもあれば、そこに至るまでの見方や考え方を振り返ることもある。その意味で、プロダクトとしての「自分なりの結論」とプロセスとしての「自分なりの結論」の両方について、振り返る場面であると言える。
本研究では、上記の3つの活動を重視していくものとし、研究副題「振り返る活動を重視して」を設定した。
なお、本年が3年目となる全体研究では、「深く考える授業」を実践するための手立ての一つである「視点を変える」活動の有効性を検証することを新たに定め研究を進める。そのため、数学科でも「振り返る」活動を通して、生徒の姿にどのような変化が期待されるかを、授業者が事前に示すこととし、授業を検証するための規準としたいと考えている。
4.本研究の目的と手立て
本研究の目的は、「考えさせる授業」を構成・実践することを通して、生徒の考える力を育成することである。また、振り返る活動を重視することにより、生徒が、自分の考えを再評価し、確証を得たり、改善や発展を図ることができるようにしていく。そこで、本研究では、次の2つの手立てを取り入れた授業づくりを進めていく。
① 生徒の知的好奇心を揺さぶり、生徒が自然と考えたくなるような問題を設定すること
先述したように、数学の授業において、生徒に考えさせる授業を構成する場合、「問題解決型」の授業を構成する。その際、扱う題材については、次のような側面が考えられる。第一に、解決が迫られている切実な現実問題や教えたい数学的な内容を含む「擬似モデル」の問題、数学の世界における問題などを、数学を使って解決することに主眼がおかれた授業である(昨年度の公開研究会における2本の授業はこれにあたる)。第二に、事象の構造をつかむために、それらの間にある関係を捉えたり、仕組みを調べたりすることに主眼がおかれた授業である。いずれの授業においても、教師は、その題材の数学的な背景まで含めた全体構造や、生徒の実態を踏まえた予想反応例について、緻密に教材研究を深めておく必要がある。
② 振り返る活動を取り入れること
振り返る活動を取り入れることによって、生徒が問題解決型の授業において、見いだしたことがらやそこに至るまでの過程を再評価し、確証を得たり、改善や発展を図ったりすることができるようにする。具体的には次の3つの活動を取り入れていく。
A.「作業」を通して振り返る活動
B.授業ノートへの記述を通して振り返る活動
C.他者との相互作用を通して振り返る活動
5.研究の内容
(1) 教材を開発し、実際に授業実践を行い、生徒が考えたくなるような数学的に内容の豊かな教材を探る。
(2) 授業の最中や授業後の生徒の様子を観察し、「振り返る活動(A~C)」のあり方を探る。
(3) 授業実践を本校数学科のカリキュラムに位置づけ、追実践を行うなどの継続した研究にしていく。
《参考・引用文献》
○杉山吉茂(1977)、「第1章 考えることと教育」「2「考える」態度や能力を伸ばす指導」、
『教育学研究全集 第13巻 考えることの教育』、第一法規、PP.41-57
○島田茂 編著(1977)、『算数・数学科のオープンエンドアプローチ』、みずうみ書房
○松原元一 編著(1987)、『考えさせる授業 算数・数学』、東京書籍
○半田進 編著(1995)、『考えさせる授業 算数・数学 実践編』、東京書籍
○松原元一(1990)、『数学的な見方考え方 子どもはどのように考えるか』、国土社
○山梨大学教育人間科学部附属中学校(2005~2014)、研究紀要
○文部科学省(2008)、『中学校学習指導要領解説数学編』、教育出版


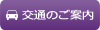



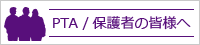

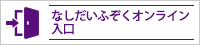

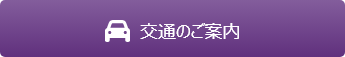
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp