平成22年度 国語総論
平成22年度国語科研究主題
「伝え合う力」を高める授業の工夫
1.主題設定の理由
学習指導要領の国語科の目標は、「伝え合う力を高める」と「国語に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる」の二段から構成されている。この目標は新学習指導要領でも変わっていない。
「伝え合う力を高める」とは、新学習指導要領解説で「人間と人間との関係の中で、互いの立場や考えを尊重し言語を通して適切に表現したり正確に理解したりする力を高めること」と定義されている。「かかわり」をキーワードにした本校の過去6年間の研究では、全体総論にもあるように「情報を受信することで内的に理解を深める」ことに重きを置いた。これは上の解説の言葉を借りれば、「正確に理解する力を高める」ということになる。今年度は、「学習活動で得た『かかわり』を生徒が振り返り、整理し、発信する」、つまり「適切に表現する力」に着目して研究を進める方向で動き出した。もちろん「正確に理解する力」と「適切に表現する力」はそれぞれ独立したものではなく、それぞれが緊密に関連し合っているものである。理解したものを表現することによって、そこに他者との響き合いも加えて、より理解を深める。これを繰り返していくことで、「伝え合う力」は高まっていくと考える。
2.全体研究との関わり
本校校内研究では、研究の内容として3つの柱をあげている。この3つを本校国語科はどのようにとらえるのかを以下に述べたい。
1)「かかわり」を見出す課題・活動の設定について
本校校内研究においては、3つの「かかわり」(学習内容の関連性)をあげている。これは、過去6年間の研究の継続でもある。先にも述べたように「正確に理解する力」を高めるために、今年度も教材開発、発問の工夫を中心に研究を進めていく。3つの「かかわり」を本校国語科では以下のように考える。
(1)教科の学習内容同士の「かかわり」
国語科の各領域や言語事項で学習する個々の知識や技能を、個々の知識や技能の獲得だけの学習に終わらせるのではなく、領域を越えて互いに活用できるという視点から、国語科の学習内容や学習事項をとらえ直す。
例えば、「読むこと」の学習で身につけた「構成をとらえる」という能力が、「書くこと」の学習で「構成を効果的に使いながら書く」といった言語の活用にいかされる。あるいは、「話すこと」の学習で、「構成に気をつけながらスピーチをする」といった活用にいかされる。などである。
(2)教材の持つ学問の体系的な「かかわり」について
学習指導要領に記されている各領域で学習する知識や技能を系統的にとらえていく。例えば、C領域「読むこと」の特有の知識や技能がある。また、説明的な文章と文学的な文章では、それぞれ特有の読み方がある。また、同じような文学的な文章ではあっても、現代文と古文とでは、やはり読み方が違ってくる。それぞれの文種に特有の読み方を系統的に学ばせ、その一つ一つの読み方がかかわりを持って、総合的に読解力を深められるようにしていく。また、それぞれの文種で身につけた読み方の言語能力が他の文種にも生かされることを学ばせることで、より学問の体系的なかかわりを見いだすことにつながると考えている。
(3)教材と日常事象との「かかわり」について
わたしたちは、多くの場合、日常事象とのかかわりの中で言語を活用していると考えられる。情報を受信するときも発信するときも、そこには常に受信者・発信者の持つ、ものの見方や考え方が影響を与えている。例えば、文学的な文章の読解を行うとき、そこには単純にスキル的な文章の読み方を身につけているだけでは割り切れない読み方というものも存在する。その作品に触発された読者の経験や体験に裏打ちされたものの見方や考え方が存在して、作品の読み方が深まるということもある。学習内容を真に身につけるためには、学習者が日頃また過去においてどのような経験や体験をしていて、それが教材にどのようにかかわりを持ってくるのかを考えていかなければならない。
これら3つの「かかわり」をいかし、「正確に理解する」という視点から国語科の知識や技能をとらえ、授業を工夫していくことで、本校校内研究のテーマに迫っていきたい。
2)学んだことを伝える活動について
新学習指導要領の言語活動例を視野に入れながら、学習したことについて、自分の言葉できちんと記述する、友人同士で伝えあうなど、他者と響き合う場、生徒が学習したことを目的や状況に応じて表現する場を設定することで、生徒自身が、より「適切に表現する力」を高めることになると考えている。
3)「学びを見とる評価」について
生徒が学んだ基礎的な知識・技能が真の習得になっているのかを見とるためには、各領域の特徴に合わせた方法を考えていく必要がある。カルテ、ポートフォリオ、ワークシート、ノートなど従来行ってきた見とりの方法をもう一度見直し、さらに「適切に表現する力」が習得できているかを見とるための方法を探っていきたい。
3.研究内容
1)研究の方向性
全体総論でも指摘されているとおり、本校生徒の実態を考えると、「知識」は身に付いているが、「活用」できていない、という傾向が見られる。昨年度までの研究から「正確に理解する」ことはできても、「適切に表現する」ことができていないということである。「適切に表現する力」が高まり、表現する楽しさを味わうことで、さらに「正確に理解する」こととの関連を知ることで、学ぶ意欲へとつなげていきたい。
「伝え合う力」の育成は、国語科のつけるべき力として要となる力である。そこで、本校校内研究で示した3つのかかわりを生徒自身が見いだし、表現する活動をどのように仕組んでいけば(方法)、「伝え合う力」が高まるかを検証していく。
2)研究内容
「伝え合う力」を高めるためには、どのような方法が有効であるかについて考えていきたい。
(1)基礎的な知識・技能の体系化
教師側は意図して学習を仕組んではいるつもりでも生徒側からはこの授業で身につけたことや内容がハッキリせず、そのため新たに出会った教材などに対しても過去の学習がいかされず、つまりかかわりを見いだせないことが多かったのではないか。
この現状を打破するためには、教師が教材分析をしたり、授業を構成したりする上で、視点として持っている知識や技能を、生徒自身が持つようになることが大切ではないかと考えた。基礎的な知識・技能を生徒が持つことによって、生徒自身が学習に自主的・主体的に参加できるようになり、理解力や表現力も高まっていくものと考えている。この基礎的な知識や技能を本校国語科では「学習用語」ととらえ、これまで取り組んできた。
個々の教師が生徒の実態や年間(あるいは3年間)のカリキュラムの中に、どの知識・技能を教えるかをよく吟味し計画的に指導計画等に位置づけていくことが大切である。もちろん各教師の目標の設定によっても与える知識・技能は変わるであろう。ただ、意識的・計画的に知識・技能を生徒に教えることで、授業がより幅の広い・厚い内容のものになると考えている。
本校国語科で考えた基礎的な知識・技能を教える教材別計画表を整理していく。
(2)言語活動の工夫
活動を仕組んだだけでは生徒が「伝え合う力」を高めることには当然ならない。その活動が基礎的な知識・技能を活用するための、生徒自身が考えるに値する教材の開発、発問や課題設定および目的の明確化が必要である。また、授業(または単元)のはじめや途中、あるいは終末において教師が的確な説明や示唆的な説明をすることによって、生徒の中にある考えや思いが整理されたり、つながったりするなど、かかわりが見いだされる大きな手助けとなるであろう。
(3)理解の視覚化
気づいたことや考えたこと、思いついたことなどを視覚化して整理したり、広げたりすることで「理解する力」「表現する力」がよりよく育つのではないかと考えている。そこで、以下に示すような視覚化させる具体的な方法を、授業の中で仕組んで行きたい。
- 「トゥルミンモデル」を使った論理構成の分析(説明的な文章の読解)
- 「ホワイトボード」を使っての説明・分析(文学的な文章の読解・討論)
- 「マインドマップ」を使った思考の表面化(作文やスピーチなどの題材・話材集め)
- 「マンダラート」を使った発想の広がり (作文やスピーチなどの題材・話材集め)
- 「一枚ポートフォリオ」を使用した思考の変容の見取り
(一単元をとおした授業の感想の見取りと変容) - 「授業感想の集積」(ノートへの記入・振り返り)
- 「三色ペン」を使用した読解(文章読解の際の思考の分類)
- 「カード」を使った文章構成の分析(説明的な文章の読解) など
このような視覚化させる方法を学習活動に取り入れることで、今やるべきことや学んでいること、自分が持っているものの見方や考え方、感じ方などを意識に上らせる(意識化させる)、さらにその手助けとして目に見える形で作業をする(視覚化させる)ことをとおすことでかかわりがはっきりして、「理解する力」「表現する力」が高まると考える。さらに、自分自身の振り返り、教員による見とりにもつながるであろう。
4.今年度の研究の方向性
今年度は以下の点を具体的に整理し、これらが、「かかわりを見いだし、表現する活動」に有効であり、「伝え合う力」を高めるために効果があったかを検証し、今後の授業に活用できるようにまとめていく。
(1)基礎的な知識・技能の活用
学習用語を具体的に整理し、各教材や単元に配置していく。
(2)言語活動の工夫
「かかわりを見いだし、表現する」ためにはどのような言語活動が有効か。具体的な教材、発問や課題設定、目的の視点を増やし、有効性について検証する。
(3)理解の視覚化
「かかわりを見いだし、表現する」ために、視覚化が有効であるか。また「見とり」の対象としても有効であるかを検証していく。
また、三年次計画の最終年度でもあるため、以上の3つを年間指導計画に位置づけていく。


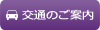



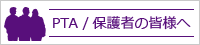

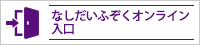

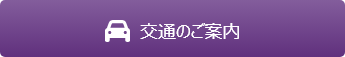
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp