研究概要
知の再構成を目指して
「かかわり」を生かした学習過程の工夫
<3年計画の3年次>
これまで本校では、生徒に「真の理解に近づけさせ、学ぶことの楽しさに気づかせる」ことをねがい、学習内容の関連性(「かかわり」)を生かした学習課題・活動を基にした授業づくりの研究をすすめてきた。生徒が記憶として覚えている知を関連付けて考えることで、より確かな知を身に付けさせる学習は、生徒の学びに対する姿勢を築く助力になったと考える。この研究において、内的な理解は深まったと考えられるものの、学習過程における生徒の「表現力」と、生徒が考えたことをどのように返すかという「評価」については課題を残した。これらの課題に取り組むために学習過程全般において「かかわり」(学習内容の関連性)を生かす工夫について考える。
平成20年3月、新学習指導要領が告示された。この新学習指導要領は、学校教育法で定められた学力観とPISAなどに見られる世界的な学力観の流れを汲んでいる。本校においても、新学習指導要領で求められているものを検討してきた。そして、いくつかのキーワードに着目した。まず、義務教育期に押さえるべき基礎的な知識・技能の「習得」。そして、基礎的な知識・技能を「活用」して課題解決する「思考力・判断力・表現力」である。さらに、これらをバランスよく育成することで、主体的に課題に取り組む態度、すなわち「意欲」を養うことができるというものである。このように見てみると新学習指導要領の具現化に、本校の研究を活用することでさらなる効果を生むことが可能であると考えた。
すなわち、知識・技能の習得、それらを活用させる学習課題・活動を学習内容の関連性「かかわり」を基に仕組むことで、思考力・判断力・表現力を養おうというものである。ただし、前述したようにこれまでの本校の研究は、生徒自身のもつ知識や概念を関連付けて考えさせる「内化」を深めるものであり、思考力の育成を軸に据えたものであった。そこで、本研究では、判断力・表現力にも着目し、内的に得た知識や概念を社会に向けて発信すること、つまり「外化」を仕組むことで、これらをバランスよく育成することができると仮定した。つまり、発信するためには、自分がもっている知識や概念をもう一度見つめ直し、相手や状況によって「再構成」しなくてはならない。このように、もう一度作り直す機会を学習過程の中に組み込み、内的な方向と外的な方向へ考えを揺さぶる学習サイクルを積み重ねることで、学びへの意欲と学習内容の理解の向上を図りたい。
具体的には以下の3点を柱と設定している
Ⅰ 「かかわり」(学習内容の関連性)を生かした学習課題・活動の設定
生徒がそれまでに身に付けた知識や技能などを総動員して、関連付けて考える場面の設定を仕組む。つまり、知識や技能を活用させる課題作り、そして、生徒自らの力で関連性を見いだせるような活動の設定である。具体的な活動例として、観察、実験、調査、操作、作業などが考えられる。
Ⅱ 伝える学習活動
考えたこと、学んだことを言語活動などを通して発信させる場を設定することで、生徒自身の考えを整理・構成させる。具体的には記述、説明、批評、証明、スピーチ、討論などが考えられる。相手のことを意識したり、表現の仕方を考えたりすることは、判断力や表現力の育成につながる。
Ⅲ 学びの評価
自らが、どのように学んだのかについて振り返り評価する。生徒自身が学びをモニタリングすることで、より確かな基礎的な知識・技能の習得につなげさせる。また、学習過程を意識させることで、活用することができる知識や技能に「再構成」する。
この3点を学習過程にバランスよく設定することで、新学習指導要領で求めている知識基盤社会に生きる力の育成を目指したい。


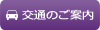



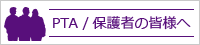

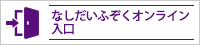

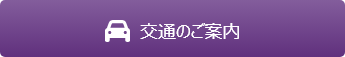
 yamanashi.ac.jp
yamanashi.ac.jp